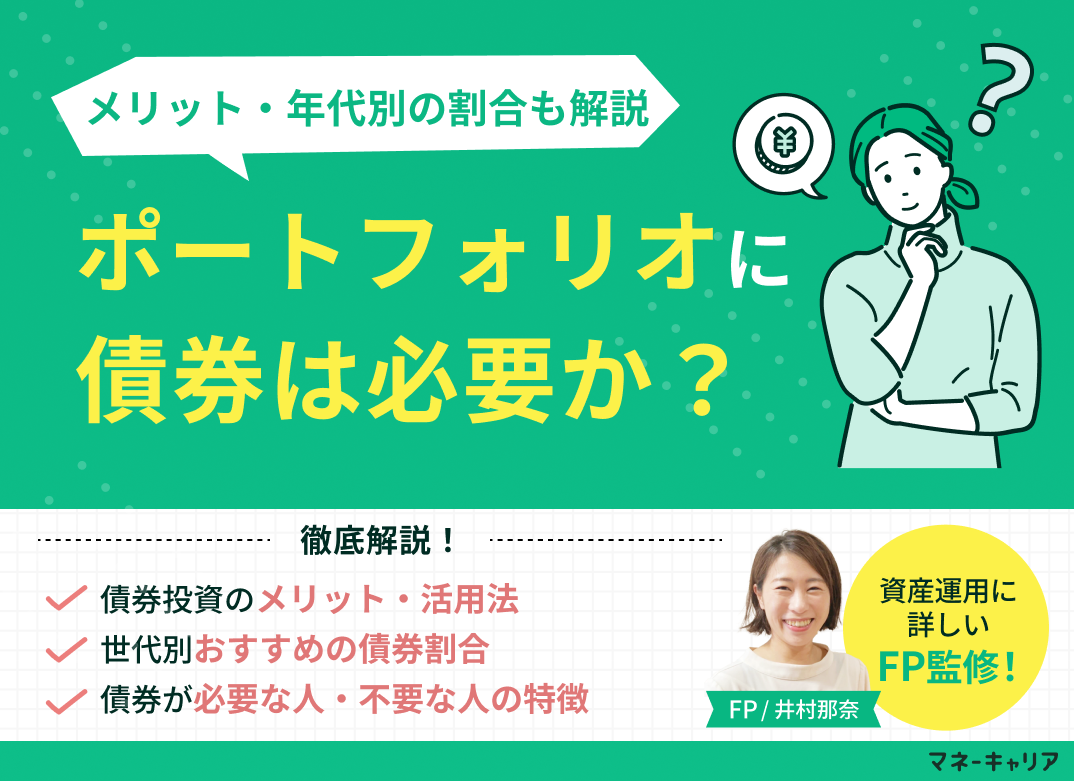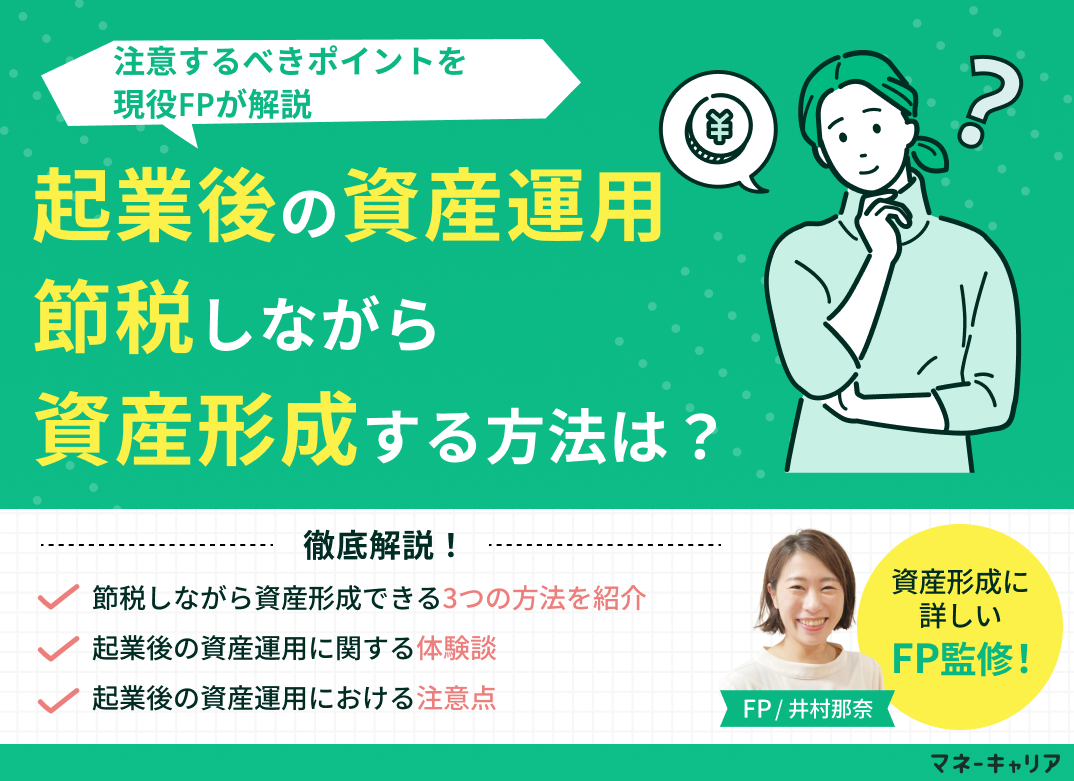「投資信託をほったらかし運用したいけど、本当にうまくいくの?」
「投資信託のほったらかし運用をやってもいいケースを知りたい」
と感じている方も多いのではないでしょうか。
- 結論、投資信託のほったらかし運用は、手間をかけずに資産形成を続けたい人にとって有効な方法です。
ただし、完全に放置するのではなく、定期的な確認や商品選びの工夫は必要です。
この記事では、投資信託のほったらかし投資による運用のポイントについて詳しく解説します。
さらに、運用する際のポイントや失敗例も紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。
- 投資信託で、ほったらかし運用を始めようか迷っている方
- 忙しくて投資にあまり手間をかけたくない方
- 自分に合った投資信託の選び方がわからない方
- リスクを抑えた投資方法や資産配分の考え方を知りたい方

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- 投資信託のほったらかし運用とは?
- 100万の投資信託を放置した場合のシミュレーション
- 年利3%の場合
- 年利5%の場合
- 年利10%の場合
- 投資信託のほったらかし運用でお悩みなら無料FP相談で解決!
- 投資信託のほったらかし運用のポイント
- 手数料が低い投資信託を選ぶ
- 途中でむやみに売買しない
- 非課税制度を活用する
- 年に1回は資産配分を見直す
- 投資信託でほったらかし運用したい場合の銘柄の選び方
- ほったらかし投資信託の失敗例を紹介
- 無理やり資金を捻出して投資してしまう
- 早期売却を繰り替えしてしまう
- 勧められた金融商品に安易に投資してしまう
- 投資信託のほったらかし投資のメリット
- 投資信託のほったらかし投資のデメリット
- 投資信託はどれくらい放置すべき?
- 運用報告書の純資産残高をチェック
- 投資信託を売却するタイミングを見極める
- 投資信託のほったらかしは運用の仕方が大切【まとめ】
投資信託のほったらかし運用とは?
投資信託のほったらかし運用とは、事前に運用方針やルールを設定して、その後は放置しておく投資方法です。
そのため、市場の短期的な値動きに一喜一憂することなく、長期的な資産成長を目指します。
具体的には、毎月一定額を積み立てる「積立投資」と組み合わせることで、投資のタイミングを分散させてリスク回避を行います。
投資信託のほったらかし運用は、投資初心者や忙しい方でも取り組みやすい投資方法として注目されている一方、ほったらかしても問題がないようにリスク管理を念入りに行う必要があります。
次の章では、ほったらかしのポイントを解説するのでぜひ参考にしてください。
100万の投資信託を放置した場合のシミュレーション
- 年利3%
- 年利5%
- 年利10%
年利3%の場合

年利5%の場合

投資信託を年利5%で運用した場合、資産の増え方はさらに加速します。
■10年後 1,647,010円
■20年後 2,712,641円
■30年後 4,467,745円
5%の利回りでは、30年後に元本の4倍以上になる計算です。5%の利回りは中程度のリスクとリターンを示しており、長期的な資産形成においては非常に有効です。
利回りとしては現実的な目標といえるでしょう。
年利10%の場合

投資信託を年利10%で運用した場合、資産の増え方は劇的です。
■10年後 2,707,042円
■20年後 7,328,074円
■30年後 19,837,400円
10%の利回りはかなり強気なものですが、複利の力で30年後には元本の17倍以上になる可能性があります。市場の状況によっては大きな変動があるので、リスク許容度の高い投資家がめざす利回りです。
今回のような高いリターンを狙う場合は、より慎重な銘柄選びが重要です。
投資信託のほったらかし運用でお悩みなら無料FP相談で解決!
投資信託をほったらかしで運用したいなら、無料FP相談を活用することをおすすめです。
FPに相談すれば、収入やライフプランに合わせた最適なほったらかし運用の仕方をアドバイスしてもらえます。
また、積立のペースや目標金額、長期的な資産の配分についても、あなたの考えや不安に寄り添って一緒に考えてもらえます。
投資初心者の方や商品選びに不安がある方は、まずはFPに相談してみましょう。
FPへの相談なら、無料で相談できるマネーキャリアがおすすめです。
- 投資信託を使った、ほったらかし運用の適切な進め方がわかる
- 自分の収支や目標に合った積立額や資産配分を提案してもらえる
- 投資信託に詳しい専門家が、中立の立場でアドバイスしてくれるから安心
投資信託のほったらかし運用のポイント
ここでは、投資信託のほったらかし運用のポイントとして以下を紹介していきます。
- 手数料が低い投資信託を選ぶ
- 途中でむやみに売買しない
- 非課税制度を活用する
- 年に1回は資産配分を見直す
手数料が低い投資信託を選ぶ
ほったらかし運用ポイントの一つ目は、手数料が低い投資信託を選ぶことです。
なぜなら、長期運用ではコストの差がリターンに大きく影響するからです。
同じような値動きをする商品でも、信託報酬が高いと運用益が目減りしてしまいます。
たとえば信託報酬が年0.5%と1.5%では、30年後には数十万円以上の差が出ることもあります。
そのため、インデックス型など手数料が低めの商品を中心に選ぶのがおすすめです。
途中でむやみに売買しない
ポイントの二つ目は、途中でむやみに売買しないことです。
なぜなら、市場の上下に惑わされて売買を繰り返すと、間違ったタイミングで売買して損をするリスクが高まるからです。
特に初心者の場合、値下がり時に不安になって売却し、その後の回復で機会損失をしてしまうケースがよくあります。
そのため、一度買ったら基本的に持ち続ける姿勢を保つことが、長期的なリターンを得るために重要です。
一時的な値動きに左右されず、冷静に運用を続けることで、資産形成を安定して進めることができます。
非課税制度を活用する
ポイントの三つ目は、非課税制度を活用することです。
なぜなら、NISAやiDeCoなどの非課税制度のある運用方法を利用すれば、運用益にかかる税金を抑えることができ、最終的なリターンを大きく高められるからです。
たとえば、通常の口座で得た利益には約20%の税金がかかりますが、NISAやiDeCoなら非課税でそのまま利益を受け取れます。
そのため、長期的に資産を増やしたい方は、これらの制度を積極的に活用するのがおすすめです。
ただし、NISAは利益を非課税で受け取れる一方、iDeCoは運用中は非課税で受取時に優遇課税される仕組みであり、それぞれ取り扱いが違うので注意してください。
年に1回は資産配分を見直す
ポイントの四つ目は、年に1回は資産配分を見直すことです。
なぜなら、目標やライフプランに変化があれば、運用方針も柔軟に調整する必要があるからです。
たとえば、転職や結婚、子どもの誕生などのライフイベントが起これば、将来必要な資金の時期や金額も変わってきます。
そのため、少なくとも年に1度は運用状況を確認し、自分のリスク許容度や目標に合った配分かどうかをチェックしましょう。
定期的な見直しを行うことで、長期投資の効果を最大化しやすくなります。
投資信託でほったらかし運用したい場合の銘柄の選び方
ほったらかし運用では、自分のリスク許容度に合った銘柄を選ぶことが重要です。
投資信託のリスクとリターンは「国内債券<海外債券<国内株式<海外株式」の順で高くなります。
たとえば、国内債券は安定性が高くリスクは低いですがリターンも控えめで、海外株式は高い成長が期待できる一方、為替や政治のリスクがあるため分散投資のバランスが大事です。
また、個々の商品ごとに特徴が異なるため各商品の詳細も事前に確認することが大切です。
ほったらかし運用する場合は事前準備の徹底や正しい選び方を意識するようにしましょう。
ほったらかし投資信託の失敗例を紹介
投資信託でほったらかし投資をする場合、いくつかの失敗例が挙げられます。
主な失敗例は以下のとおりです。
- 無理やり資金を捻出して投資してしまう
- 早期売却を繰り替えしてしまう
- 勧められた金融商品に安易に投資してしまう
無理やり資金を捻出して投資してしまう
ほったらかし投資信託の失敗例の1つめは、無理やり資金を捻出して投資してしまうことです。
無理やり資金を捻出して投資をすると、急な出費に対応できず、資産を取り崩すことになりかねません。
途中で資産を取り崩すと長期投資で得られるメリットを受けられず、結果として失敗につながる可能性があります。
投資は余剰資金で行うのが基本であり、無理のない範囲で継続することが大切です。
無理やり資金を捻出してしまわないように、投資前に家計を見直し、余剰資金の範囲内で投資を始めましょう。
早期売却を繰り替えしてしまう
ほったらかし投資信託の失敗例の2つめは、早期売却を繰り返してしまうことです。
株価の上下に一喜一憂して早期売却を繰り返すと、安価で手放すことになり、損失につながる可能性があります。
本来、投資信託は長期的に運用をしてリスクを抑えながら資産を増やす仕組みです。
そのため、短期目線で早期売却を繰り返してしまうと、長期投資のメリットを受けられません。
ほったらかし投資信託を失敗しないためには、相場の一時的な変動に左右されず、長期的な視点で保有を続けましょう。
勧められた金融商品に安易に投資してしまう
ほったらかし投資信託の失敗例の3つめは、勧められた金融商品に安易に投資してしまうことです。
自分のリスク許容度に合っていなかったり金融商品の運用目的が自分に合っていなかったりすると、失敗につながる可能性が高まります。
また、金融商品によっては手数料が高く、長期運用に不向きなケースもあります。
ほったらかし投資で失敗を防ぐためには、勧められた商品であってもすぐに購入せず、商品の内容を理解したうえで判断しましょう。
投資信託のほったらかし投資のメリット
投資信託のほったらかし投資のメリットは以下の3つあります。
- 少額から始められる
- 投資のタイミングを考える必要がない
- 長期にわたって投資をすると、収益が安定する傾向がある
投資信託は少額から始められるため、気軽に投資できます。
毎月の積立投資も可能なので、無理のない範囲で資産形成を進められるでしょう。
また、定期的に一定額を投資し続けることで、平均単価を抑えられる「ドルコスト平均法」により、投資のタイミングを考える必要がありません。
さらに、長期にわたって投資をすると収益が安定する傾向があり、複利効果により時間が経過するほどに資産の増加ペースが加速します。
このように投資信託のほったらかし投資は、特に初心者や長期の資産形成を考える方にとって有効な投資手段だといえるでしょう。
投資信託のほったらかし投資のデメリット
投資信託のほったらかし投資のデメリットは、以下の2つです。
- 短期で大きな利益を得るのが難しい
- 繰上償還される可能性がある
ほったらかし投資は長期的な視点での資産形成を目的としており、短期的な値動きに反応して売買するスタイルではありません。
そのため、急激な市場の上昇局面では、より多くのリスクをとって積極的な投資をしている投資家に比べて利益が少なくなることがあります。
また、「繰上償還」という投資信託などの金融商品が予定より早く償還されることによって、投資家の大量の換金などで純資産残高が一定水準を下回ると運用会社が期限を繰り上げて償還する可能性があります。
投資信託のほったらかし投資で失敗を防ぐためにも、これらのデメリットを把握した上で定期的に投資先の状況をチェックすることが重要です。
投資信託はどれくらい放置すべき?

- 運用報告書の純資産残高をチェック
- 投資信託を売却するタイミングを見極める
運用報告書の純資産残高をチェック
投資信託をどれくらい放置すべきかの1つめの判断材料は、運用報告書の純資産残高をチェックすることです。
投資信託は、一般的には最低でも5年、できれば10年以上の長期保有が推奨されます。
しかし完全に放置するのではなく、定期的に運用報告書で純資産残高が安定しているかや増加傾向にあるかを確認し、投資信託の健全性を判断しましょう。
純資産残高が大きく減少している場合は多くの投資家が投資信託を解約しており、ファンドの魅力が低下している可能性があります。
年に1~2回程度運用報告書をチェックし、純資産残高の推移を確認してください。
投資信託を売却するタイミングを見極める
投資信託をどれくらい放置すべきかの2つめの判断材料は、投資信託を売却するタイミングを見極めることです。
一般的には、以下の4つのタイミングが挙げられます。
- 資金需要の発生:子どもの教育資金など長期的に資金が必要になるタイミング
- 運用方針の変更:投資信託の運用方針が変更され、自分の方針と合わなくなったタイミング
- パフォーマンスの低下:長期的に市場平均を下回り続けているタイミング
- 手数料の上昇:運用管理費用(信託報酬)が引き上げられて手数料が高くなったタイミング
投資信託のほったらかし投資は完全に放置するのではなく、定期的なチェックと状況に応じた見直しが大切です。
投資信託のほったらかしは運用の仕方が大切【まとめ】
この記事では、投資信託を活用した「ほったらかし運用」について紹介してきました。以下に本記事の内容をまとめます。
- 投資信託のほったらかし投資は、手間をかけずに利益を上げることが可能で、長期的に資産を増やしたい人におすすめ
- メリットは「少額から始められる」「投資のタイミングを考えなくてよい」「長期投資だと収益が安定しやすい」3つある
- 一方デメリットは「短期で大きな利益を得るのが難しい」「繰上償還される可能性がある」2つがある
- 銘柄を選ぶときのポイントとして、国内債券<海外債券<国内株式<海外株式の順で考慮することが大事