
・住宅ローン控除の相談先がわからない
・住宅ローン控除でいくら現在されるのか知りたい
こんなお悩みをお持ちではありませんか?
住宅ローンを組む際、住宅ローンの残高に応じて所得税が控除される仕組みがあります。
とはいえ「税金の話は難しくてよくわからない」「どこかに相談するにも適切な相談先がわからない」という方も多いのではないでしょうか。
そこで、この記事では「住宅ローン控除と相談先」をトピックに説明していきます。この記事を読むことで費用を最大限抑えて住宅ローンの支払いを進められます。
まずは、住宅ローンの控除に関しておすすめの相談先は下記の通りです。
※各相談窓口のランキングは、「相談窓口の信頼性」「予約のしやすさ」など住宅ローン相談窓口の評価基準で定めた8つの観点から決定しております。

この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。メディア実績:<テレビ出演>テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ!」
>> 谷川 昌平の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- 住宅ローン控除(減税)の相談先を選ぶ際のポイント
- おすすめの住宅ローン控除(減税)の相談先5選
- FP(ファイナンシャルプランナー)
- 金融機関
- 税理士
- 国税局電話相談センター
- 自治体の税務相談窓口
- 住宅ローン控除(減税)を最大限に活用するためのヒント
- ローンの借り入れ計画を見直す
- 繰り上げ返済のタイミングを考慮
- 共働きの場合の名義設定
- 控除対象となるリフォームの活用
- 適切な書類管理と申告
- 専門家への相談
- 住宅ローン控除(減税)に関するよくある間違い事例
- 資格要件に関する落とし穴
- 金銭的な落とし穴
- 物件選択の落とし穴
- 生活変化による落とし穴
- 制度変更の落とし穴
- 住宅ローン控除以外の減税方法
- 住宅ローン控除の相談先に迷ったらおすすめの無料サービス
- 住宅ローン控除についても無料で相談できる:マネーキャリア
- 【まとめ】住宅ローン控除(減税)の仕組みを把握して損しないようにしよう
住宅ローン控除(減税)の相談先を選ぶ際のポイント
住宅ローン控除(減税)の相談先には複数の種類があり、どこを選ぶべきか迷う方は多いです。
そこで、まずはこちらの診断チャートで自分にピッタリな相談先を見つけてみましょう。

おすすめの住宅ローン控除(減税)の相談先5選
住宅ローン控除について相談する際は、専門知識や中立性、費用などのバランスを考慮して相談先を選ぶことが重要です。ここでは、それぞれの特徴を踏まえた5つの相談先を紹介します。
| 相談先 | FP (ファイナンシャルプランナー) | 金融機関 | 税理士 | 国税局電話相談センター | 自治体の税務相談窓口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 相談料 | 無料または有料 (初回無料の場合も) | 無料 | 5,000円~3万円程度/回 (税理士によって異なる) | 無料 | 無料 |
| こんな方に おすすめ | ライフプラン全体を見直したい方 住宅・教育・老後資金に不安がある方 | 住宅ローンや資産運用の アドバイスを受けたい方 | 複雑な税務処理や 節税対策をしたい方 | 税金の基本的な内容について 確認したい方 | 住民税や固定資産税など 地域の税について相談したい方 |
| 相談方法 | 対面 オンライン 電話 (FPにより異なる) | 店舗窓口 オンライン | 対面 電話 オンライン | 電話 | 対面 (予約制) |
| 詳細 | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら |
住宅ローン控除について相談する際は、自分の状況や求めるアドバイスの内容に合わせて、最適な相談先を選びましょう。自分のニーズに合った相談先を見つけてください。
FP(ファイナンシャルプランナー)

住宅ローン控除に関する相談は、家計のプロであるファイナンシャルプランナー(FP)にも依頼できます。
FPは住宅ローンに関する基本的な知識があり、実績が豊富なFPも数多く在籍しています。
FPの強みは、住宅ローン控除だけでなく、教育費や老後資金なども含めた総合的な視点でアドバイスできる点です。
 FPの特徴
FPの特徴
金融機関

住宅ローンを組む予定の銀行や信用金庫などの金融機関も、住宅ローン控除について相談できる窓口の1つです。金融機関での相談の最大のメリットは無料であることと、住宅ローン商品について専門的な知識を持つスタッフから直接情報を得られる点です。
金融機関では、自社の住宅ローン商品と住宅ローン控除を組み合わせた返済シミュレーションを作成してくれるため、毎月の返済額や控除による節税効果を具体的に把握できます。
 金融機関の特徴
金融機関の特徴
税理士

税理士は税金の専門家であり、住宅ローン控除の仕組みや適用条件について最も詳しいアドバイスが期待できる相談先です。とくに、複雑な確定申告や税金計算が必要な場合には、税理士のサポートが非常に心強いでしょう。
税理士に相談するメリットは、個人の所得状況や家族構成などを考慮したうえで、最適な控除方法を提案してくれる点です。
 税理士の特徴
税理士の特徴
国税局電話相談センター

国税局が運営する電話相談センターは、住宅ローン控除を含む税金に関する質問に無料で回答してくれる公的な窓口です。税務当局から直接情報を得られるため、制度の正確な内容や適用条件について信頼性の高い回答が期待できます。
電話相談センターの最大のメリットは、完全無料で利用できること・匿名でも相談可能な点です。
 国税局電話相談センターの特徴
国税局電話相談センターの特徴
自治体の税務相談窓口

お住まいの市区町村では、定期的に税務相談会を実施している場合があります。自治体の税務相談窓口の大きな特徴は、無料で専門家(多くの場合は税理士)に相談できる点です。専門知識を持った専門家からのアドバイスが無料で受けられるため、コストを抑えながら質の高い相談ができます。
自治体の相談窓口では、住宅ローン控除だけでなく、不動産取得税や固定資産税など地方税に関する情報も得られる点が強みです。また、地域の不動産事情に詳しいため、地域特有の制度や優遇措置についても情報を得られる可能性があります。
さらに、住民税からの控除についても詳しく説明してもらえるでしょう。
 自治体の税務相談窓口の特徴
自治体の税務相談窓口の特徴
住宅ローン控除(減税)を最大限に活用するためのヒント

住宅ローン控除は正しく活用することで、長期間にわたり大きな節税効果が得られます。ここでは、住宅ローン控除を最大限に活用するために、以下の6つのポイントを解説します。
- ローンの借り入れ計画を見直す
- 繰り上げ返済のタイミングを考慮
- 共働きの場合の名義設定
- 控除対象となるリフォームの活用
- 適切な書類管理と申告
- 専門家への相談
将来の家計負担を軽くするためにも、6つのポイントをチェックしておきましょう。
ローンの借り入れ計画を見直す
繰り上げ返済のタイミングを考慮
住宅ローン控除は年末のローン残高に応じて算出されるため、繰り上げ返済のタイミングは慎重に検討しましょう。たとえば、年末直前に繰り上げ返済をすると、その年の控除額が減ってしまいます。控除率が0.7%であることを考えると、住宅ローンの金利が0.7%を下回る場合は、控除期間中の繰り上げ返済は実質的に損になる可能性もあります。
最も効率的なのは、控除期間(新築なら13年間)が終了した後に繰り上げ返済を行うことです。どうしても控除期間中に繰り上げ返済をしたい場合は、年始に実施することで、その年の控除額への影響を最小限に抑えられます。
共働きの場合の名義設定
共働き夫婦なら、住宅ローンの名義を上手に設定することで、控除額を増やすことが可能です。たとえば、夫婦それぞれがローンを組む「ペアローン」方式を採用すれば、二人とも住宅ローン控除を受けられます。
収入が近い夫婦の場合、二人合わせると単独で借りるよりも控除額が増えます。 ただし、ペアローンを組む際には、夫婦の合計所得金額が2,000万円を超えないことを確認しましょう。上限を超えると控除が受けられなくなるからです。
控除対象となるリフォームの活用
住宅ローン控除は新築や中古住宅の購入だけでなく、一定の条件を満たすリフォーム工事でも適用を受けられます。リフォームに関する控除の内容は以下のとおりです。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 対象工事 | 耐震改修工事 バリアフリー改修工事 省エネ改修工事 大規模修繕や模様替え(増築・改築) |
| 控除率 | 年末時点の住宅ローン残高の0.7% |
| 控除期間 | 最長10年 |
| 借入限度額 | 一般リフォーム:最大 2,000万円 認定住宅(長期優良住宅など):最大 3,000万円 |
省エネ改修や耐震改修、バリアフリー改修などが対象となります。ただし、工事費が100万円を超え、ローンの返済期間が10年以上必要です。
適切な書類管理と申告
住宅ローン控除を受けるためには、必要書類の管理と適切な申告手続きが不可欠です。控除初年度は確定申告が必須で、多数の書類を準備しなければいけません。
確定申告に必要な書類は以下のとおりです。
- 住宅ローン年末残高証明書
- 登記事項証明書
- 売買契約書または請負契約書のコピー
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 源泉徴収票
- 本人確認書類
これらの書類をきちんと保管しておかないと、申告できないため注意しましょう。2025年以降の住宅では、省エネ性能に関する証明書類が必要です。不動産会社や住宅メーカーから受け取った書類は、忘れずに整理・保管しておきましょう。
専門家への相談
住宅ローン控除は制度が複雑で頻繁に変更されるため、最新の情報を持つ専門家に相談することが効果的です。とくに税理士やファイナンシャルプランナー(FP)は、住宅ローン控除に詳しく、個々の状況に応じた適切なアドバイスが可能です。
専門家は住宅ローン控除と他の所得控除をどのように組み合わせれば税負担が最も軽減されるかといった複雑な判断をサポートしてくれます。共働き世帯には、ローンの名義の分け方や将来の収入変動への備えについて、専門家の意見が参考になるケースが多いでしょう。
住宅ローン控除(減税)に関するよくある間違い事例
住宅ローン控除は節税効果が大きい制度ですが、知識不足から思わぬ落とし穴にはまるケースがあります。ここでは、多くの方が陥りがちな間違い5つを詳しく紹介します。
- 資格要件に関する落とし穴
- 金銭的な落とし穴
- 物件選択の落とし穴
- 生活変化による落とし穴
- 制度変更の落とし穴
これらの間違い事例を知っておくことで、控除が受けられなくなるリスクを回避し、確実に節税効果を得られるでしょう。
資格要件に関する落とし穴

住宅ローン控除を受けるためには、いくつかの厳格な資格要件を満たす必要があります。よくある落とし穴が居住要件・床面積の誤解・所得制限の見落としの違反です。
代表的な事例は、次のとおりです。
- 購入後6か月以内に入居していない
- 転勤等で一時的に住まなくなった場合の手続き不備
- 入居後に賃貸に出してしまう
- 登記上の床面積と実際の床面積を誤解していた
- 共有部分を含めた誤った計算していた
- 合計所得金額3,000万円を超えていた
引き渡しまたは工事完了から6か月以内に入居し、控除対象年の12月31日まで住み続ける必要があります。たとえ転勤などで一時的に住まなくなった場合でも、手続きを怠ると控除を受けられなくなるので注意しましょう。
金銭的な落とし穴

住宅ローン控除に関する金銭面の誤解も少なくありません。
まず、控除額について、「年末のローン残高がすべて控除される」と勘違いしている方が少なくありません。 実際には、年末時点のローン残高の0.7%が控除額として適用されます。
たとえば残高が3,000万円だと、控除額は21万円(3,000万円×0.7%)です。 また、控除額には限度があります。もし所得税で控除しきれなければ、翌年の住民税でも控除が可能です。ただし、住民税から控除できる金額には、9万7,500円という上限が設定されています。
住宅ローンが高額でも、所得税・住民税の合計以上の控除は受けられないため、年収が低い方は控除額に限界があることを理解しておきましょう。
物件選択の落とし穴

住宅の種類によっても住宅ローン控除の適用条件は異なります。
とくに中古住宅を購入する場合は注意が必要です。2024年以降、新築住宅では省エネ基準適合が必須となりましたが「その他の住宅」(省エネ基準非適合)は控除対象外となっています。
ただし、2023年末までに建築確認を受けた住宅や2024年6月末までに建築された住宅については例外的に対象です。購入時期や建築確認日を確認をしましょう。
増改築工事でも住宅ローン控除を受けられますが、条件を満たさないと対象外となります。工事費用が100万円以上であることや、対象となる工事の範囲(大規模修繕や省エネ改修、バリアフリー改修など)への該当が条件です。リフォーム前に工事内容が控除対象となるか確認し「増改築等工事証明書」を確実に取得しましょう。
生活変化による落とし穴

離婚によって住宅の名義や居住者が変わると、住宅ローン控除の継続に影響が出ることがあります。住宅ローンの名義人が居住しなくなった場合、原則として控除は受けられなくなります。離婚時に住宅を取得した配偶者が居住を継続しても、ローンの名義人でなければ控除は引き継げません。
また、転職や退職で所得が大幅に減少すると、所得税額が減るため控除しきれない部分が増えてしまいます。所得税で控除しきれなかった分は住民税から差し引かれますが、上限は9万7,500円までと決まっています。無職になると、控除の恩恵を十分に受けられなくなる場合があるため注意が必要です。
制度変更の落とし穴
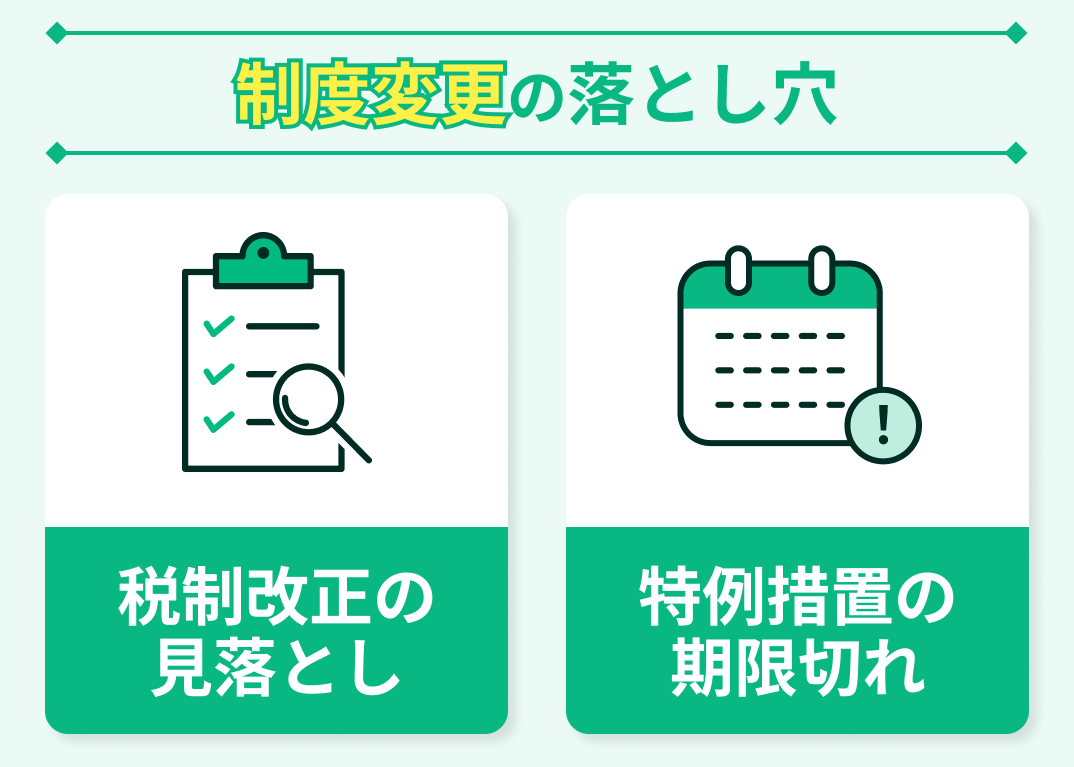
住宅ローン控除は頻繁に税制改正が行われるため、入居時期によって控除期間や借入限度額が大きく異なります。
2022年の改正では控除率が1.0%から0.7%に引き下げられ、2024年以降は省エネ基準適合が新築住宅の必須要件となりました。また、2024〜2025年入居の場合と2022〜2023年入居の場合では借入限度額にも差があります。
住宅ローン控除以外の減税方法
住宅ローン控除だけでなく、住宅購入に関連して活用できる税制優遇制度は複数あります。
受託ローン以外の主な減税方法は以下のとおりです。
- 印紙税の軽減措置
- 登録免許税の軽減措置
- 不動産取得税の軽減制度
- 固定資産税・都市計画税の軽減措置
- 認定住宅によるさらなる税制優遇
まず、契約時から引き渡しまでに適用される印紙税と登録免許税の軽減措置があります。印紙税は契約金額に応じて税率が軽減され、たとえば5,000万円以下の契約なら通常の半額になります。
住宅ローン控除の相談先に迷ったらおすすめの無料サービス

住宅ローン控除は制度が複雑で頻繁に変更されるため、専門家のアドバイスを受けると確実に控除を受けられます。税務署や国税局では基本的な制度情報は得られますが、個人の家計状況に合わせた提案は期待できません。
そこでおすすめなのがマネーキャリアのような無料FP相談サービスです。マネーキャリアには、ファイナンシャルプランナーや住宅ローン診断士などがそろっており、あなたの家庭状況や収入に合った専門家に気軽に相談できます。
特定の金融機関に属さない独立系FPからアドバイスを受けられるため、中立的な立場からの提案が期待できます。住宅ローン控除に加え、将来設計や家計の見直しも含めた総合的なアドバイスを、無料で何度でも受けられる点が大きな魅力です。
制度改正やライフスタイルの変化にも対応できるため、住宅ローン控除をしっかり活用したい方にぴったりのサービスです。
住宅ローン控除についても無料で相談できる:マネーキャリア

<マネーキャリアのおすすめポイントとは?>
・住宅ローンに関する相談実績が豊富な独立FPが数多く在籍している。
・いくら借入できるかではなく、無理なく返済できる借入金額を提案してくれる。
・担当する専門家のFP資格保有率は100%であり、顧客満足度98.6%、相談実績も80,000件以上を誇る、信頼と実績が充分にある窓口。
<マネーキャリアの利用料金>
マネーキャリアでは、プロのファイナンシャルプランナーに「無料で」「何度でも」相談できるので、相談開始〜完了まで一切料金は発生しません。

20代女性
住宅ローンのローン形態、借入先、金利タイプがわかりやすかったです!
住宅ローンの他にも投資信託のことまで分かりやすく教えて頂きました。こちらが質問したことにも丁寧に教えてくださり面談して良かったです。

30代女性
住宅ローンを中心としたライフプランの相談もできました!
たまたま見つけて申し込みをしたのですが、親身になって色々と相談に乗って頂きました。無理してローンを組もうとしていたのを思いとどまることができ、とても感謝しています。ありがとうございました!

40代男性
自分に最適な住宅ローンの借入額がわかりました!
住宅ローンの利用にあたり、現在の家計簿見直しを合わせて相談させてもらいました。自分で試算していて不安を覚えた部分が相談により解消でき、モヤモヤがなくなりすっきりしました。
【まとめ】住宅ローン控除(減税)の仕組みを把握して損しないようにしよう
ここまで、住宅ローン控除の相談先や注意点、条件などについて詳しく解説してきました。住宅ローン控除は税制改正によって内容が変わりやすく、専門的な知識が必要なため、適切な相談先を選ぶことが重要です。
理想的な相談先は、単に税金の計算だけでなく、あなたの家計状況やライフプランを含めた総合的なアドバイスができる専門家です。しかし、相談先によっては表面的な説明に終始したり、特定の金融商品を勧められたりして、必要な情報が得られないケースもあります。
そこでおすすめなのが、相談実績80,000件、満足度98.6%を誇るマネーキャリアのサービスです。マネーキャリアでは、ファイナンシャルプランナーや住宅ローン診断士があなたの家庭状況に応じて最適なサポートを提供します。個別シミュレーションをもとに無理のない返済計画を立てられるので、将来の家計も安心です。
無料相談への登録は1分で完了します。ぜひ気軽に相談して住宅ローン控除について正確に理解し、住宅ローンをお得に利用しましょう。




























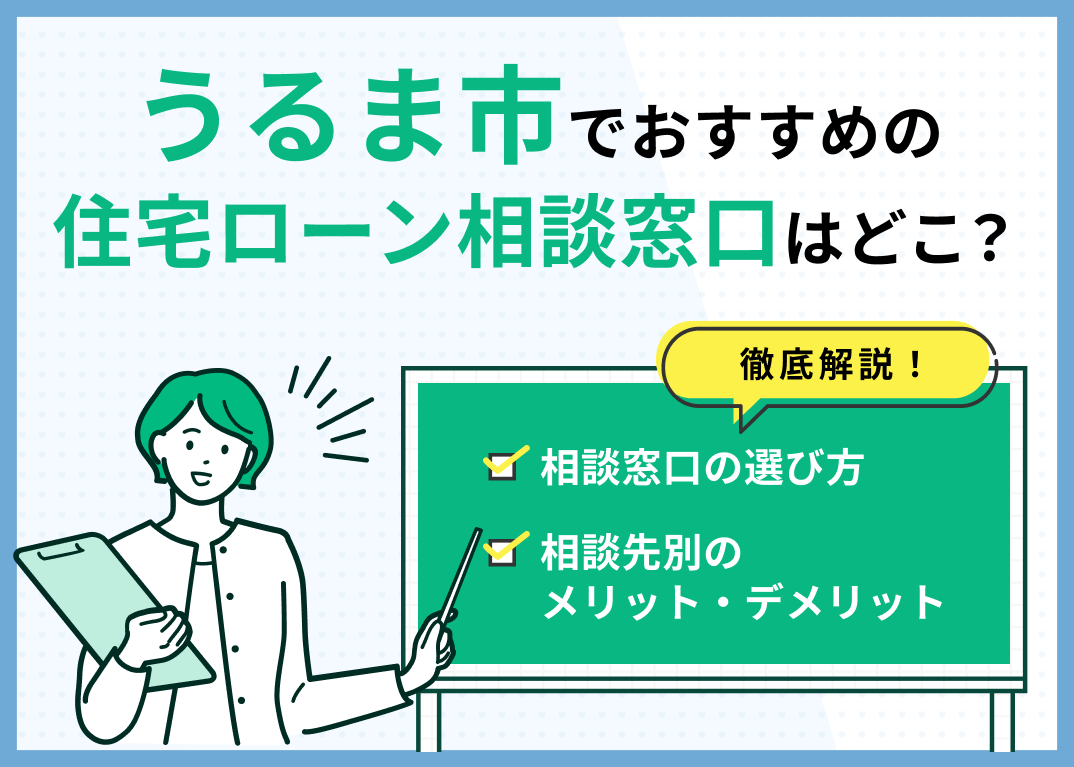
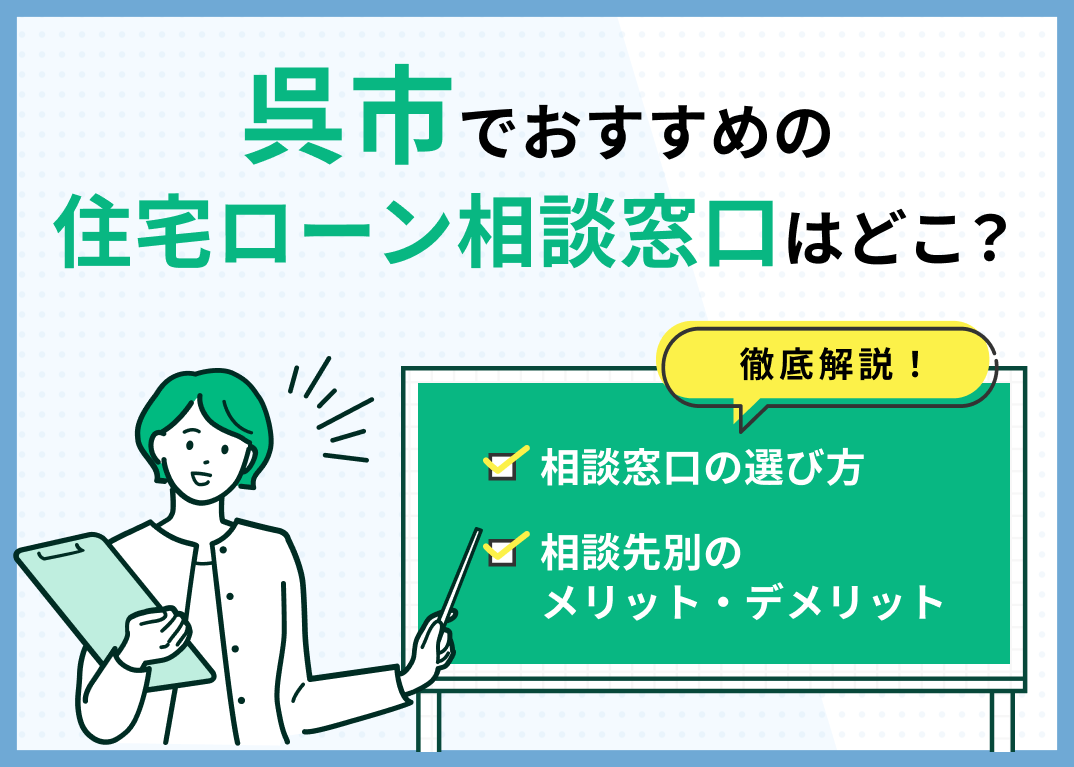
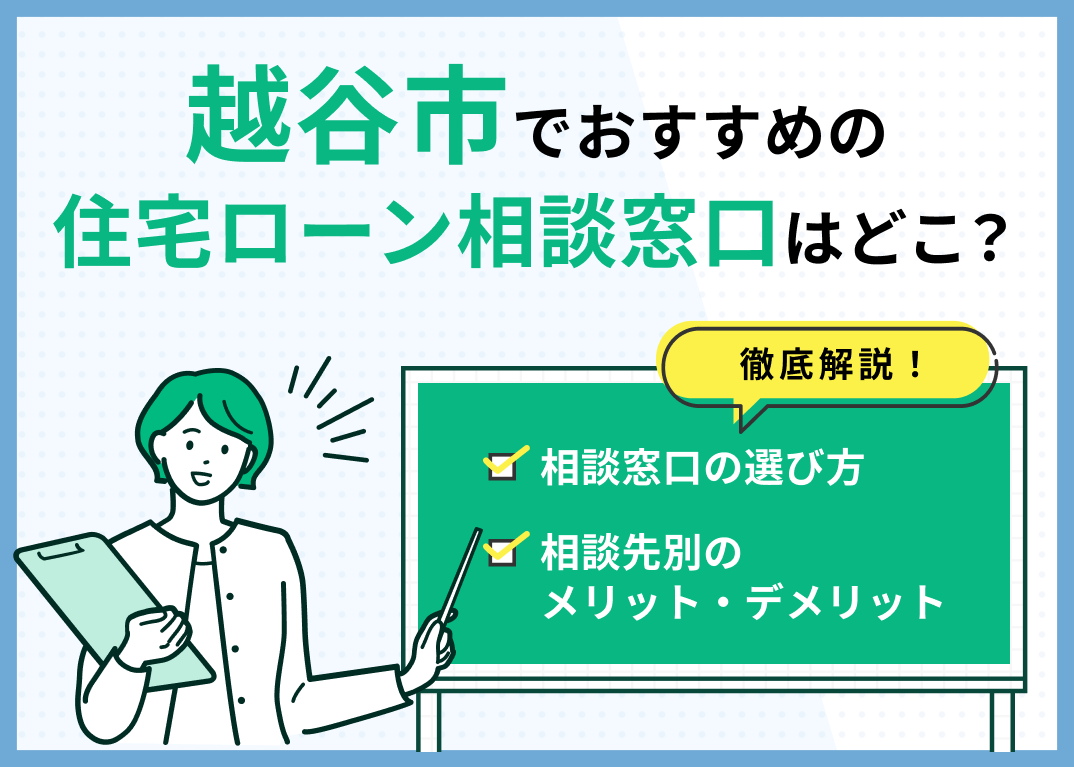
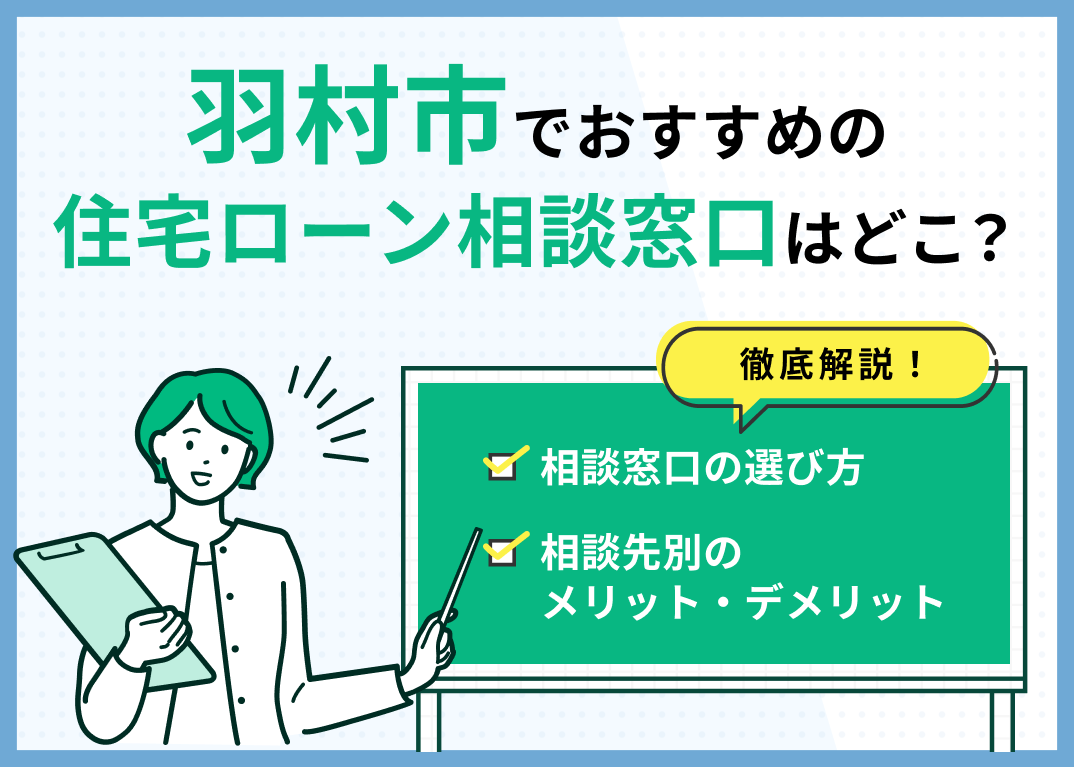
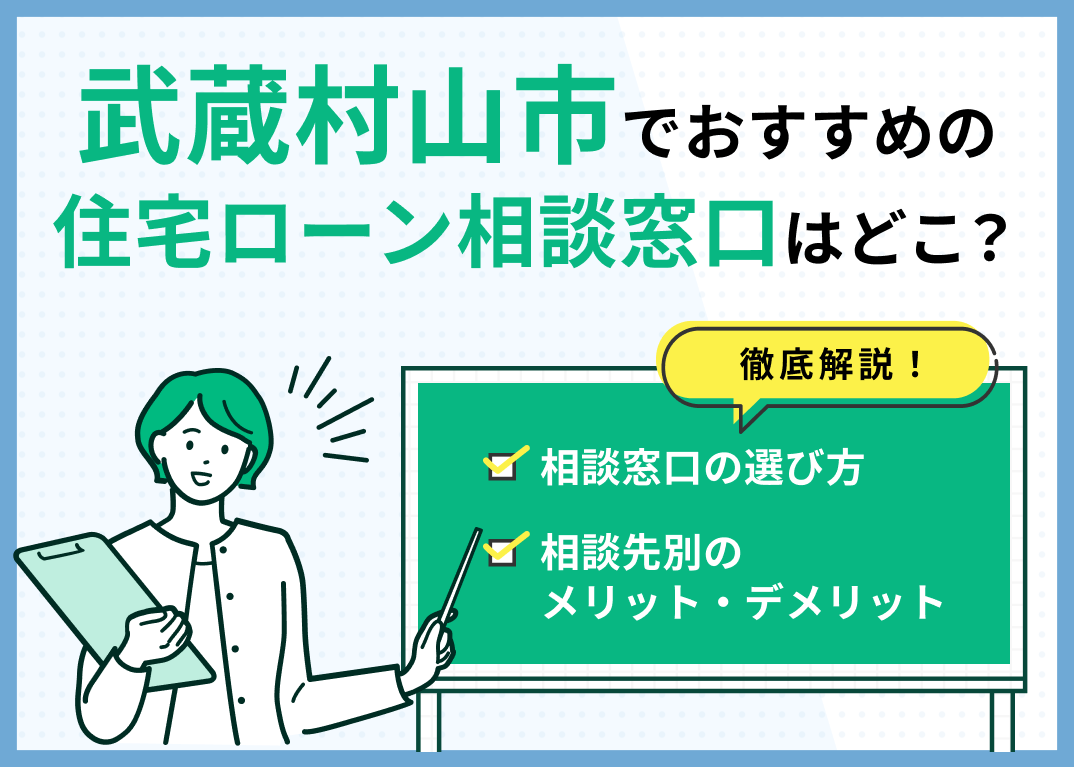
(FPの資格レベルや相談内容による)
中立的な立場からのアドバイスを求める方
将来の家計管理も含めた総合的な提案が欲しい方
独立系FPなら中立的なアドバイスが得られる
マネーキャリアなどの無料相談サービスも活用可能