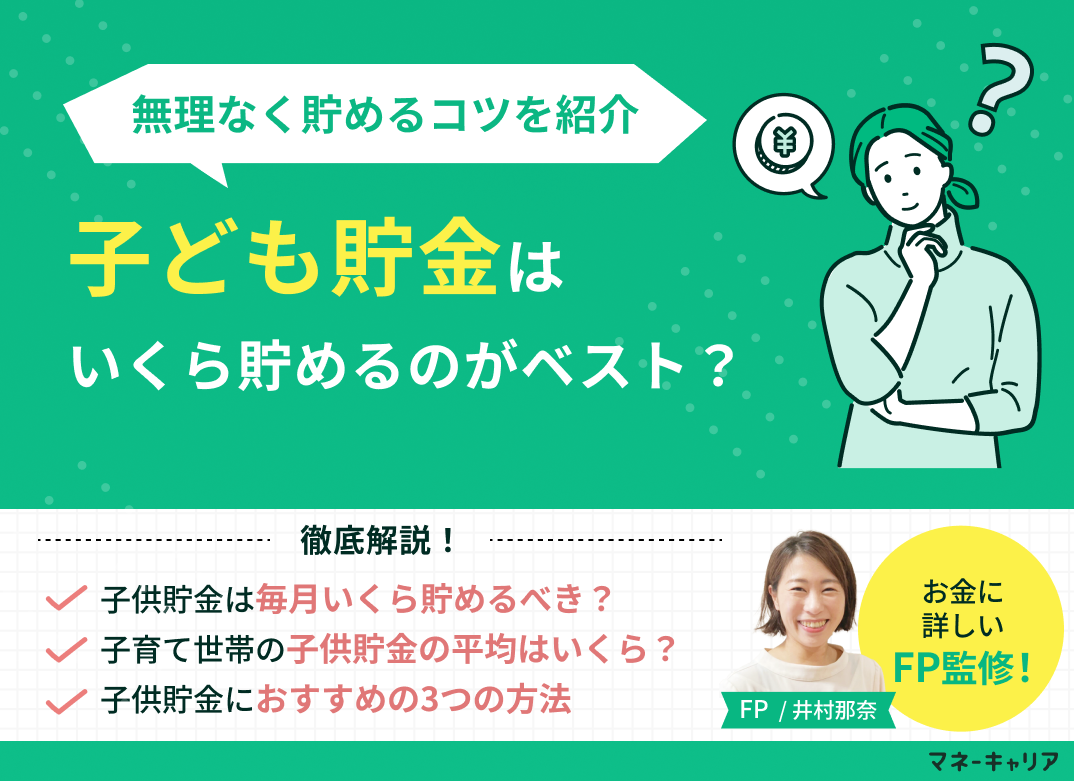
「子供の貯金って毎月いくらすればいいの?」
「大学までに必要なお金がどれくらいか分からなくて不安……」
そんな悩みや疑問を抱えている方は多いでしょう。
結論からお伝えすると、毎月の子供貯金は月1〜3万円を目安に、希望する進学先に合わせて積立額を設定するのがおすすめです。
この記事では、子供の教育費に必要な金額や平均的な貯金額、効率よく貯める具体的な方法について解説しますので、ぜひ参考にしてください。
・「子供の教育費に備えて、毎月いくら貯めればいいの?」
・「銀行預金以外で効率よく積み立てる方法はある?」
そんな方は、本記事を読むことで教育費の全体像を理解し、自分の家庭に合った無理のない貯金方法を見つけられます。
内容をまとめると
- 子供貯金は月1〜3万円が目安
- 大学までに必要な教育費は1,000万〜2,000万円
- 平均的な子供貯金額も家庭ごとに差がある
- NISAや学資保険を活用すれば効率よく貯められる
- マネーキャリアでは家庭に合った教育費の貯め方を無料で相談できる

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
子供貯金は毎月いくらがベスト?
毎月いくら子供貯金するのがベストなのかは家庭によって異なりますが、月1〜3万円を目安に、進路に合わせて積み立てるのがおすすめです。
まずは必要な教育費の総額を見積もり、そこから逆算して考えましょう。
なぜなら、目標を明確にしなければ「なんとなくの積立」で終わり、十分な資金を準備できないからです。
例えば大学まで進学する場合、幼稚園から高校までの学費に約500万〜700万円、大学に進学すればさらに国公立で約250万円、私立文系なら約400万円、私立理系では600万円以上かかります。
子供貯金はいくらあればいい?大学までに必要な教育費総額
子供貯金の目安は目標の進学先によっても異なりますが、大学入学までに400万円をひとつの目標にするとよいでしょう。
文部科学省・日本学生支援機構(JASSO)の調査によると、学校種別の学習費(保護者が支出した1年間の教育費)の目安は以下のとおりです。
| 公立 | 私立 | |
|---|---|---|
| 幼稚園 | 約18.5万円 | 約34.7万円 |
| 小学校 | 約33.6万円 | 約182.8万円 |
| 中学校 | 約54.2万円 | 約156.0万円 |
| 高校 | 公立 約59.8万円 | 私立 約103.0万円 |
参照:文部科学省「令和5年度子供の学習費調査」
| 国公立 | 私立(文系) | 私立(理系) | 私立(医・歯系) | |
|---|---|---|---|---|
| 大学(4年間の合計) | 約243万円 | 約443万円 | 約573万円 | 約2,354万円 (6年間) |
参照:文部科学省「国公私立大学の授業料等の推移」・日本学生支援機構(JASSO)「令和4年度学生生活調査」
子育て世帯の子供貯金の平均はいくら?
金融広報中央委員会の調査によると、子育て世帯の平均貯金額は以下のとおりです。
- 平均値: 1,212万円
- 中央値: 400万円
子供貯金におすすめの3つの方法
子供貯金を毎月いくらするか決まっても、どのような方法で貯金するか迷いますよね。
そこで、おすすめの子供貯金の方法を3つご紹介します。
- 銀行の積立預金・定期預金
- NISA
- 学資保険
これらの特徴を理解して組み合わせれば、より安心して準備を進められます。
それぞれの仕組みを詳しく見ていきましょう。
銀行の積立預金・定期預金
銀行の積立預金や定期預金は、シンプルで安全性の高い方法です。
元本保証があるため減るリスクがなく、確実に貯められます。
例えば、毎月2万円を18年間積み立てれば432万円になり、教育資金の一部をしっかり確保できるでしょう。
NISA
NISA(小額投資非課税制度)は、子供貯金を効率的に増やす手段として有力です。
株式や投資信託で得た利益が非課税になり、銀行預金より高い金利を期待できます。
たとえば、つみたて投資枠で月3万円を年利3%で運用した場合、18年後には約740万円に増える計算です。
学資保険
学資保険は貯蓄と保障を兼ね備えた方法です。
契約者が亡くなった場合や高度障害になった場合でも、以後の保険料が免除され、予定通りの学資金を受け取れます。
たとえば、18歳時に300万円を受け取れるプランに加入していれば、高校卒業時の入学準備金として活用可能です。
無理なく子供貯金を続けるコツ3選
貯金方法を決めたら、毎月貯金を続けられる習慣を作りましょう。
貯金を続けるには以下のようなコツがあります。
- 子供貯金専用の口座を作る
- 児童手当を貯金する
- 毎月自動で積み立てられる制度を利用する
こうした工夫を取り入れれば、無理なく続けられるはずです。
それぞれを順に確認していきましょう。
子供貯金専用の口座を作る
子供貯金を成功させるには、専用口座を作ることが効果的です。
生活費と教育資金を明確に分けることで、誤って使い込むリスクを減らせます。
ネット銀行の口座を教育費専用に設定すれば、いつでも残高を確認できモチベーション維持にもつながるでしょう。
児童手当を貯金する
児童手当をそのまま貯金に回すのもシンプルで効果があります。
なぜなら、一定額が支給されるため、計画的に教育資金を準備できるからです。
例えば、高校卒業までに受け取れる総額は約234万円で、この金額を貯めておけば高校や大学進学時の大きな助けになります。
毎月自動で積み立てられる制度を利用する
毎月自動積立制度を利用すれば、貯金が習慣化されます。
「強制的に引き落とされる仕組み」により、迷ったり忘れたりせずに確実に貯められるからです。
給与振込口座から毎月2万円を自動で積み立てれば、18年後には432万円が積み上がります。
子供貯金に関するよくある質問
最後に、子供貯金に関するよくある質問をご紹介します。
代表的な質問は以下の3つです。
- 貯金ができないときはどうすればいい?
- 毎月の積立が難しいとき、ボーナスで貯金しても大丈夫?
- 子供が2人以上いる場合はどうする?
貯金への不安を解消するために、順番に確認していきましょう。
貯金ができないときはどうすればいい?
結論として、貯金ができないときは「小さな金額からでも始めること」が重要です。
ゼロと1,000円でも積み重ねの差が大きく、金額が小さければ貯金の心理的なハードルが下がります。
毎月の積立が難しいとき、ボーナスで貯金しても大丈夫?
毎月積み立てられない場合でも、ボーナス時にまとめて貯金する方法は有効です。
年間を通して一定額を確保できれば、最終的に教育資金として機能するため、毎月が難しければボーナスを貯金しても問題ありません。
子供が2人以上いる場合はどうする?
子供が2人以上いる場合は、1人ずつ専用口座を作り「公平に積み立てる工夫」をしましょう。
将来の進学費用で不公平感が出ると、子供同士のトラブルにつながりかねないからです。




























