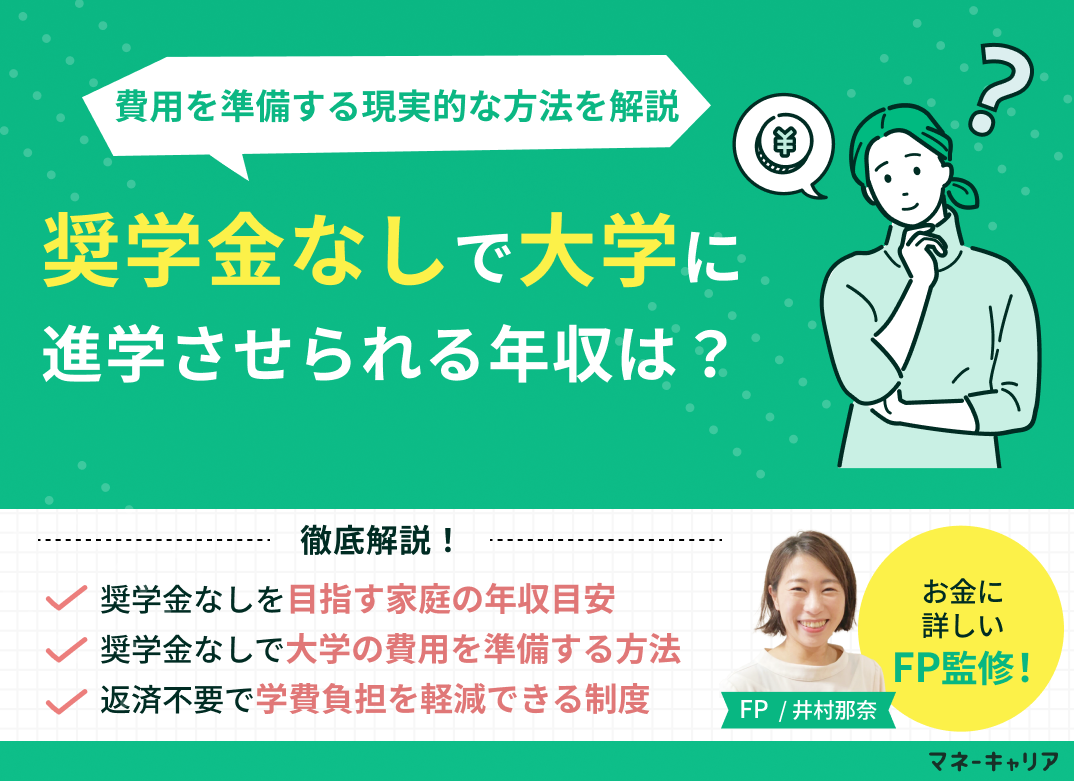
内容をまとめると
- 奨学金なしで大学進学をめざすには、年収だけでなく、学費にまわせる資金の確保力が重要です。
- 定期預金・児童手当・NISAなどを組み合わせることで、準備期間や家計に応じた現実的な備えができます。
- 大学無償化制度や学校独自の給付金を活用すれば、年収に不安がある家庭でも学費負担を軽減できる可能性があります。
- 進学費用の準備と家計の整理を同時に考えたい方は、相談実績10万件超・満足度98.6%調のマネーキャリアの活用をおすすめします。

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- 奨学金なしで大学に進学させるには年収がいくら必要か解説
- 私大進学も見据えて奨学金なしを目指す家庭の年収目安
- 奨学金なしで大学進学を実現している家庭に多い特徴
- 年収よりも重要なのは「学費にまわせるお金」の確保力
- 奨学金なしで大学の費用を準備する方法
- 定期預金や積立定期預金を活用する
- 児童手当を貯める
- 学資保険に加入する
- NISAなどで資産運用を始める
- 返済不要で学費負担を軽減できる制度
- 高等教育の修学支援新制度(大学無償化制度)
- 学校独自の給付金
- 奨学金なしで大学に進学させられるか悩んだら専門家(FP)に無料相談がおすすめ
- 奨学金なしで大学に進学させられる年収は?関連するよくある質問
- 奨学金なしで大学に通う人の割合はどれくらいですか?
- 奨学金を借りないと大学に行けない人が在学中にしておくべきことは何ですか?
- 奨学金なしで大学進学は家計の設計次第で実現できる【まとめ】
奨学金なしで大学に進学させるには年収がいくら必要か解説
奨学金なしで大学に子どもを進学させるには、年収がいくら必要か解説します。
紹介する内容は以下のとおりです。
- 私大進学も見据えて奨学金なしを目指す家庭の年収目安
- 奨学金なしで大学進学を実現している家庭に多い特徴
- 年収よりも重要なのは「学費にまわせるお金」の確保力
年収だけで判断せず、収入に対する支出のバランスや準備の仕方も含めて考えることで、自分たちに合った進学プランが見えてくるので、ぜひ参考にしてください。
私大進学も見据えて奨学金なしを目指す家庭の年収目安
奨学金なしで大学進学を目指す場合、「年収○万円あれば安心」と一律に言い切るのは難しいものです。
なぜなら、進学先(国公立・私立)や通学スタイル(自宅通学・一人暮らし)、大学進学までに準備できた額などによって、必要な費用が大きく変わってくるからです。
とはいえ、進学プラン別に学費の目安を知っておくことは可能です。
大学4年間の授業料と入学金の合計は、国公立で約240万円、私立文系で約400万円、私立理系で約550万円が目安とされています(※)。
この目安をもとにすると、例えば私立文系で一人暮らしの場合、年間の授業料約80万円と、仕送り年84万円(月7万円✕12ヵ月想定)で、合計160万円以上の支出が見込まれます。
このケースで進学資金の準備がゼロの場合、例えば世帯年収600万円・手取り約450万円の家庭では、年間支出の35%以上を学費に充てることになり、生活費のやりくりが難しくなる可能性があるでしょう。
※参照1:国公私立大学の授業料等の推移|文部科学省 / 令和3年度 私立大学入学者に係る初年度学生納付金 平均額|文部科学省
奨学金なしで大学進学を実現している家庭に多い特徴
奨学金なしで大学進学を実現している家庭には、いくつかの共通した傾向が見られます。
まず、教育費の優先度を高く設定し、住宅や車の購入を後回しにしているケースが多くあります。
また、児童手当をそのまま貯金に回したり、学資保険を早くから契約しておくことで、大学入学時にまとまった資金を用意している家庭も目立ちます。
さらに、実家から通える大学を選ぶことで、下宿代や生活費を抑える工夫をしている家庭も少なくありません。
こうした工夫は、特別な高収入がなくても実践できることばかりです。
今の家計のなかで教育費の優先順位を見直し、できる工夫を取り入れることが、奨学金に頼らない進学を実現する第一歩になるでしょう。
年収よりも重要なのは「学費にまわせるお金」の確保力
結局のところ大切なのは、年収の多さではなく、学費にまわすお金をどれだけ確保できるかという点です。
たとえ世帯年収が高くても、住宅ローンや車のローン・生活費などの負担が大きければ、教育費に回せるお金は限られてしまいます。
一方で、例えば年収600万円台の家庭でも、子どもが小さいうちから日々の支出を見直し、教育費を最優先に積み立てていけば、奨学金に頼らず大学進学を実現できる可能性は十分にあります。
家計全体のバランスを意識しながら、教育費・生活費・老後資金など、目的別に分けてお金を管理する習慣を、できるだけ早くから取り入れることが大切です。
奨学金なしで大学の費用を準備する方法
奨学金を借りずに大学へ進学させたい場合は、できるだけ早くから計画的に備えることが大切です。
ここでは、準備期間が短い順に、進学資金を確保するための代表的な4つの方法をご紹介します。
紹介する方法は以下のとおりです。
- 定期預金や積立定期預金を活用する
- 児童手当を貯める
- 学資保険に加入する
- NISAなどで資産運用を始める
準備期間の長さやリスク許容度に応じた方法を選ぶことで、ムリのない範囲で進学資金を確保しやすくなるので、ぜひ参考にしてください。
定期預金や積立定期預金を活用する
数年以内に大学資金が必要なご家庭には、定期預金や積立定期預金のような、確実に積み立てられる方法が安心です。
元本保証があり、短期間で着実に貯めたい人に向いているためです。
定期預金は、まとまった資金を一定期間預けて運用する方法です。
満期までは原則引き出せないため、“使わない仕組み”としての効果もあり、学費目的で計画的に貯める際に活用しやすいでしょう。
積立定期預金は、毎月決まった金額を普通預金から自動で振り替える貯金方法です。
給与日に合わせて設定すれば、給与天引きのような感覚で、無理なく続けやすいでしょう。
児童手当を貯める
児童手当を教育資金として活用することで、奨学金なしで大学進学を目指しやすくなります。
定期的に受け取れる公的支援を、そのまま使わず積み立てることで、計画的な資金準備ができるからです。
児童手当は高校生年代まで支給対象となっており、3歳未満は月15,000円、それ以降は月10,000円(第三子以降は月30,000円)と、長期で受け取れる制度です。
例えば中学1年生の4月から積み立てを始めると、高校卒業までに72万円を準備できる計算になります。
なお、教育費専用の口座を用意しておけば、日々の生活費と分けて管理できるため、使い込みを防げて安心です。
学資保険に加入する
学資保険に加入することも、奨学金なしで大学の費用を準備する有効な手段のひとつです。
決まった保険料をコツコツ積み立てることで、進学時にまとまった保険金(満期金や祝い金)を受け取ることができ、教育費がかさむタイミングの備えになります。
また、多くの学資保険には、"親に万が一のことがあった場合、以後の保険料支払いが免除される"というしくみがあり、家計のリスクヘッジにもつながります。
こうした特徴から、学資保険は、計画的に積み立てたい人や、万が一に備えながら教育資金を準備したい人にとって安心感のある選択肢です。
なお、一般的に学資保険は子どもが小さいうち(0〜6歳)でないと新規加入できないため、加入を検討する場合は早めの判断が必要です。
NISAなどで資産運用を始める
NISAなどで資産運用を始めることで、奨学金なしで大学の費用を準備する選択肢が広がります。
運用益が非課税となるNISAの制度を活用すれば、効率的に教育資金を増やせる可能性があるからです。
とくに、NISAのなかでも“つみたて投資枠”なら、少額からコツコツ積み立てられるため、教育費を長期的に準備したい家庭に向いています。
10年以上の長期運用によって、価格の変動リスクをおさえやすくなる点も安心材料です。
ただし、投資は元本保証ではないため、生活費とは分けた“余裕資金”でおこなうことが大切です。
「余裕資金を少しずつ運用しながら教育資金を増やしたい」と考えている方は、選択肢のひとつとして検討してみてもよいでしょう。
返済不要で学費負担を軽減できる制度
返済不要で学費負担を軽減できる制度を、2つ紹介します。
紹介する制度は以下のとおりです。
- 高等教育の修学支援新制度(大学無償化制度)
- 学校独自の給付金
いずれも申請や選考が必要なため、早めに情報を集めておくことが大切です。
制度のしくみを知っておけば、学費の不安を少しでも減らせる可能性があるので、ぜひ参考にしてください。
高等教育の修学支援新制度(大学無償化制度)
高等教育の修学支援新制度(大学無償化制度)は、経済的な事情で進学をあきらめなくてすむように設けられた支援制度です。
対象は、住民税非課税世帯や、それに準ずる収入の家庭に属する学生で、一定の学業基準を満たす必要があります。(子どもが3人以上の世帯など)
支援内容は、授業料・入学金の減免と、返済のいらない給付型奨学金の2つにわかれます。
例えば私立大学では、入学金約26万円、授業料約70万円が減免されます。
加えて給付型奨学金として、自宅通学で月38,300円、自宅外なら月75,800円の支援が受けられます。
国公立大学でも同様の支援があり、制度を活用することで進学費用の不安を大きく減らせます。
学校独自の給付金
大学によっては、独自の給付金制度や学費サポートが充実しているところもあります。
これらの制度は、世帯年収に関係なく、“学力”や“人物評価”などで選ばれる点が特徴です。
なかには、授業料の全額を免除する制度を設けている大学もあり、進学時の負担を大きく減らせます。
募集要件や支給条件は学校ごとに異なるため、早めに資料を取り寄せて確認しておくことが大切です。
“給付金制度のある大学を選ぶ”という視点も、奨学金に頼らない進学の一歩になります。
奨学金なしで大学に進学させられるか悩んだら専門家(FP)に無料相談がおすすめ
奨学金なしで大学に進学させられる年収は?関連するよくある質問
奨学金なしで大学進学を目指す家庭が気になる、よくある質問を2つご紹介します。
紹介する質問は以下のとおりです。
- 奨学金なしで大学に通う人の割合はどれくらいですか?
- 奨学金を借りないと大学に行けない人が在学中にしておくべきことは何ですか?
現状を知り、今できる準備を考えることで、進学に向けた判断がしやすくなるので、ぜひ参考にしてください。
奨学金なしで大学に通う人の割合はどれくらいですか?
日本学生支援機構の調査によると、奨学金なしで大学へ通っている学生は、全体の55.0%(※)にのぼります。
つまり、半数以上が家計や貯蓄、ほかの支援制度などを活用して進学していると考えられます。
「奨学金を使うのが当たり前」と感じていた方には、少し意外な数字かもしれません。
しかし、"進学=奨学金"と思い込まず、今の家計でできる備え方を見つけることが大切です。
まずは“知ること”から始めれば、進学資金の選択肢がぐっと広がる可能性があります。
奨学金を借りないと大学に行けない人が在学中にしておくべきことは何ですか?
奨学金を借りて大学に通う場合は、在学中に“卒業後の返済を見すえた準備”をしておくことが大切です。
例えば、日本学生支援機構の奨学金貸与・返還シミュレーションなどを使って、毎月の返済額や返済期間をあらかじめ確認しておくと、借入額を決める判断材料になります。
また、アルバイト収入を管理したり、固定費を見直したりする習慣をつけておくと、卒業後の生活設計にも役立ちます。
借りる前から"どう返していくか"を意識することで、将来の不安を減らしながら大学生活を送ることができるでしょう。
奨学金なしで大学進学は家計の設計次第で実現できる【まとめ】
奨学金なしで大学へ進学させることは、家計の設計次第で実現できる可能性が高まります。
具体的には、必要な年収目安を把握しつつ、家計の支出を見直しながら、準備期間に応じて定期預金・学資保険・NISAなどを活用する工夫がポイントになります。
とはいえ、自分の家庭の場合は進学までにどれだけ準備が必要か、どんな制度が使えるのか、迷ってしまう方も少なくありません。
奨学金に頼らない資金計画に不安を感じる方は、専門家(FP)への相談をおすすめします。




























