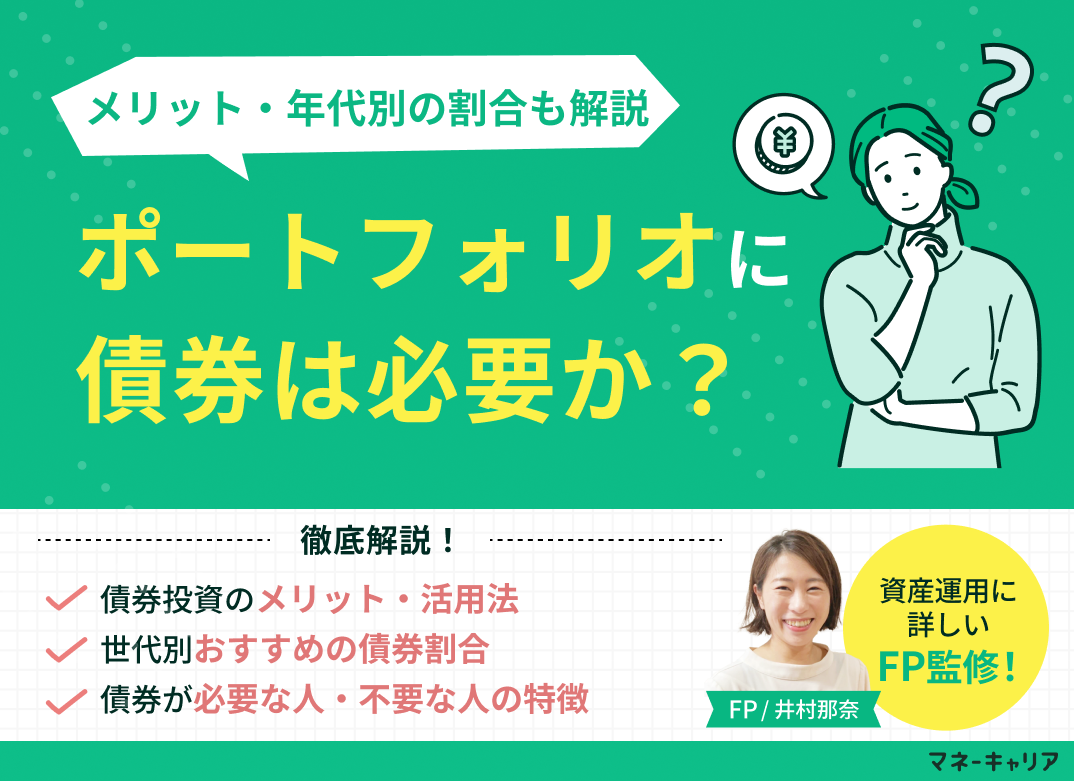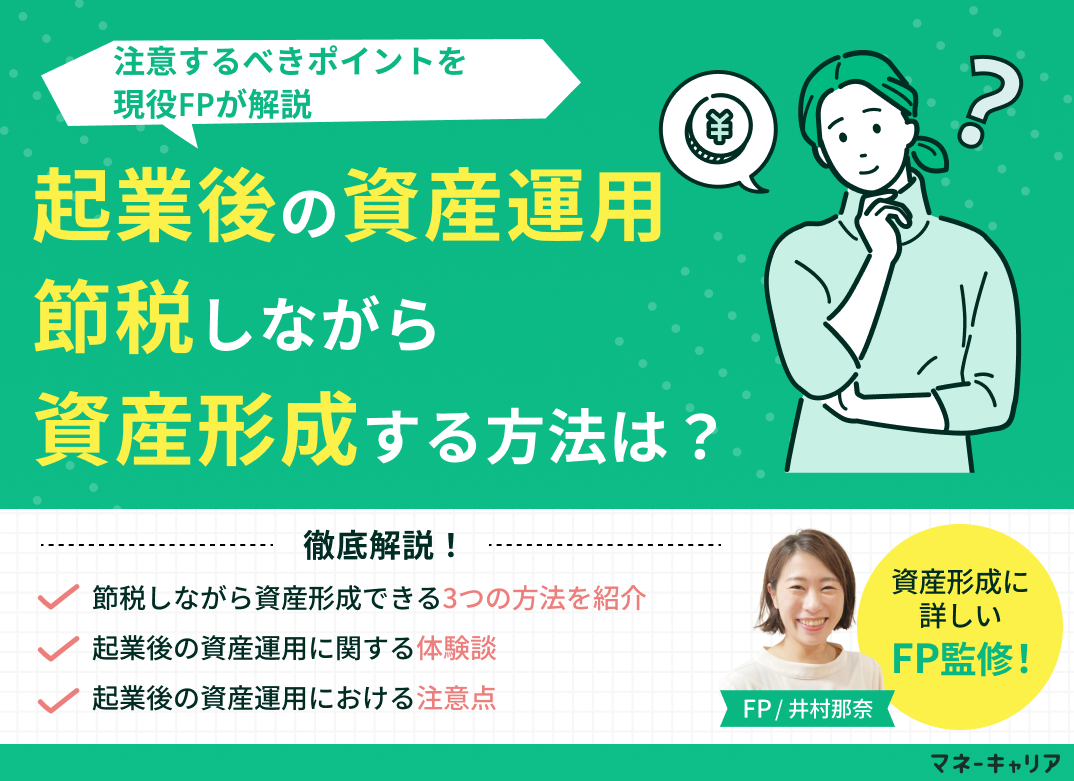この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- 5年ごと利差配当付き保険とは?かんたん説明
- 配当金の仕組み
- 無配当保険と利差配当保険の違い
- 利差配当付保険は5年ごと配当型と毎年配当型どちらがいい?
- 利差配当付き保険についてお悩みなら無料FP相談で解決!
- 5年ごとの利差配当付保険が合わない人の特徴
- 貯蓄目的がある人
- 途中解約するかもしれない人
- 5年ごとの利差配当付保険が合っている人の特徴
- 保障をベースに資産形成も少し期待したい人
- 商品選びや運用判断に手間をかけたくない人
- 元本割れリスクを抑えたい人
- 配当金が課税対象となるかは受け取り時期次第
- 保険契約期間中の受取の場合
- 保険金の支払日開始日以降
- 保険金受け取りと同時
- 保険の種類によっても課税対象になる場合がある【参考】
- まとめ:5年ごと利差配当付き保険に関する相談はマネーキャリアへ
5年ごと利差配当付き保険とは?かんたん説明

5年ごとの利差配当付保険とは契約から5年ごとに、保険会社の運用実績によって剰余金が生じた場合に配当金を受け取れる保険のことです。
保険会社は契約者から受け取った保険料を株式や債券などで運用しており、その運用成果が予定利率を上回った場合に配当金として還元されます。
ただし、配当金の支払いは保証されているものではなく、運用実績が悪化した場合は配当金が支払われない年もあります。
そのため、配当金のみを目的とした保険加入をすると、実際に受け取れなかった際に後悔する可能性があるので注意しましょう。
配当金の仕組み
加入時に設定された予定利率と、決算によって確定した利率の差によって、余剰金が発生すれば配当金がいくらもらえるかが決定します。
保険会社が保険料を設定するときに利用する利率が、次の3つの利率です。
| 利率 | 利率の決め方 |
|---|---|
| 予定利率 | 国が発表している標準利率をもとに、保険会社が独自で決めた利率 |
| 予定死亡率 | 年齢や性別ごとに、過去の統計からどれくらいの被保険者がなくなるのかを予測 |
| 予定事業率 | 事業運営に対する必要経費がどれくらいになるのかを予測 |
しかし、予測した利率通りになるとは限らず、決めた利率よりも高い利率で運用されて余剰金が発生すると、配当金として契約者に分配されるようになっています。
無配当保険と利差配当保険の違い
配当金の分配をおこなわない保険を無保険保険といい、利差配当付き保険と比べると保険料が安く設定されています。
配当金を支払わないことを前提に、保険料を決定するときに用いる基礎利率を、実際の経験値に限りなく近い数値に決定することで、保険料を抑えられているのです。
利差配当付き保険と無配当保険を比較してみると、以下のようになります。
| 配当金の違い | 配当金の有無 | 保険料 |
|---|---|---|
| 利差配当付き保険 | あり ※確定ではない | 予測の数値を用いて計算するため保険料が高くなる |
| 無配当保険 | なし | 配当金を分配する必要がないため保険料を安く設定 |
5年ごと利差配当付き保険は、配当金の有無やいくら出るという確約はありませんが、配当金がいくらか出れば嬉しいですよね。
しかし、同じ保障内容でも、無配当保険の方が保険料は安くなるため、毎月の負担を減らしたい人にはおすすめです。
利差配当付保険は5年ごと配当型と毎年配当型どちらがいい?
利差配当付保険の配当金は決まっていないため、5年ごと配当型と毎年配当型どちらがいいかは一概には言えません。
両者で配当金の頻度や配当方法などの特徴が異なるため自分の目的に合ったタイプを選ぶのがおすすめです。
特徴の違いは以下のとおりです。
| 比較項目 | 毎年配当型 | 5年ごと配当型 |
|---|---|---|
| 配当の頻度 | 年に1回 | 5年に1回 |
| 配当金額 | 少額をこまめに受け取る | 数年分をまとめて受け取るため 比較的まとまった金額になることが多い |
| 配当の使い道 | こまめに生活費などに 活用しやすい | まとめて使う目的 (旅行・家電購入など)に向いている |
| 複利運用 (据え置き型の場合) | 再配当による 積立効果が出やすい | まとまった再配当が可能で 効率的に増やせる場合もある |
| 向いている人 | 少額でも毎年の 配当を実感したい人 | 配当の活用タイミングを 自分で調整したい人 |
利差配当付き保険についてお悩みなら無料FP相談で解決!
利差配当付き保険についてお悩みの場合は無料FP相談で解決しましょう。
専門家(FP)に相談することであなたのライフプランや希望条件に合った保険選びについてアドバイスを受けることができます。
また、将来の資産形成や保障の内容に関する相談もできます。
そのため、利差配当付保険に加入することに対して漠然とした不安がある場合はとりあえず専門家(FP)に相談してみるのがおすすめです。
FPに相談するなら無料で相談できる「マネーキャリア」がおすすめです。
- 利差配当付き保険に加入するべきかどうかを判断
- 数十社の中から保険商品を比較検討できる
- 年齢/家族構成/これから起こるライフイベントに合わせて必要な保障内容を解説可能
- 納得いくまで何度でも相談無料
5年ごとの利差配当付保険が合わない人の特徴
5年ごとの利差配当付保険が合わない人の特徴は以下のとおりです。
- 貯蓄目的がある人
- 途中解約するかもしれない人
貯蓄目的がある人
貯蓄目的で保険に加入しようとしているなら、5年ごと利差配当付き保険はおすすめできません。
利差配当付保険は、あくまで保険であるため、資産形成を目的として考えるには効率が悪いからです。
払込保険料の額に比べて、配当額が小さくなりやすい傾向にあるため、保険を利用して貯蓄したい場合は、貯蓄性のある保険に加入した方がリターンを期待できます。
生命保険のなかでも、貯蓄性のある保険といえば、以下の2種類の保険で、貯蓄の目的に合わせて利用できます。
- 老後の生活資金として貯蓄するなら「個人年金保険」
- 目指す貯蓄額に達したら解約返戻金を受け取る「終身保険」
途中解約するかもしれない人
5年ごと利差配当付き保険に加入しても、6年以内に解約する可能性があるなら、いくら配当金が高くても受け取ることができないため、おすすめできません。
生命保険会社の運用によって配当金が決まったとしても、加入後6年目となる保険契約しか分配の対象にはならないのです。
配当金を受け取る権利を持てるのは、5年ごと利差配当付き保険の場合、6年目の契約応答日に契約が有効である保険契約者となります。
加入後5年以内に保険を解約する可能性があるなら、そもそも配当金を受け取ることはできません。
6年目の契約応当日まで継続する予定がなく解約する可能性があるなら、 5年ごと利差配当付き保険よりも保険料の安い無配当保険に加入した方がお得だと言えるでしょう。
5年ごとの利差配当付保険が合っている人の特徴
5年ごとの利差配当付保険が合っている人の特徴は以下のとおりです。
- 保障をベースに資産形成も少し期待したい人
- 商品選びや運用判断に手間をかけたくない人
- 元本割れリスクを抑えたい人
これらの特徴を理解して、自分に合った保険選びの参考にしましょう。
保障をベースに資産形成も少し期待したい人
5年ごとの利差配当付保険は、保障をベースに資産形成も少し期待したい人に適しています。
この保険は万が一の際の死亡保障を確保しながら、保険会社の運用実績に応じて配当金を受け取れる可能性があります。
純粋な投資商品と比べるとリターンは控えめですが、保障機能がついているため安心感があります。
「投資は怖いけれど、預貯金だけでは物足りない」と感じている方にとって、バランスの取れた選択肢と言えます。
商品選びや運用判断に手間をかけたくない人
5年ごとの利差配当付保険は、商品選びや運用判断に手間をかけたくない人に適しています。
投資信託や株式投資では、定期的な商品の見直しや売買のタイミングを判断する必要がありますが、この保険では保険会社が運用を代行してくれます。
契約者は保険料を支払うだけで、あとは保険会社のプロが資産運用を行ってくれるため、投資の知識がなくても安心です。
また、市場の動向を常にチェックしたり、運用方針を変更したりする必要もありません。
忙しい会社員や、投資に時間を割きたくない方にとって、手間のかからない資産形成手段として魅力的な選択肢です。
元本割れリスクを抑えたい人
5年ごとの利差配当付保険は、元本割れリスクを抑えたい人に適しています。
この保険は株式投資や投資信託と比べて、価格変動が比較的穏やかで安定性が高い傾向があります。
ただし、利差配当付保険は保険料が割高になる場合や資産形成として使用するには非効率というデメリットがあります。
そのため、「投資に興味はあるけど、リスクは避けたい」という方にとって、少額ではあるものの、多少のリターンが望める利差配当付保険は検討すべき選択肢の一つです。
配当金が課税対象となるかは受け取り時期次第
配当金が課税対象となるかは受け取り時期によって異なります。
主な受け取り時期は以下のとおりです。
- 保険契約期間中の受取の場合
- 保険金の支払日開始日より後の受取の場合
- 保険金受け取りと同時の受取の場合
保険契約期間中の受取の場合
保険契約の保険料を支払っている期間中に配当金を受け取った場合、その配当金に対して税金がかかることはありません。
配当金を受け取るために継続した保険の保険料は、必要経費としてみなされます。
支払った保険料の方が多ければ、受け取った配当金に課税されることはないのです。
年末調整や確定申告では、以下のように計算して生命保険料控除の金額を申告しましょう。
1年間に支払った保険料-受け取った配当金=生命保険料控除の金額
生命保険料控除証明書には、配当金額も記載されているので、確認しなら転記しましょう。
保険金の支払日開始日以降
保険金の支払いが始まった日以降に配当金を受け取る場合は、課税対象となる可能性が高くなります。
この時期に受け取る配当金は、既に保険契約が終了した後の受け取りとなるため、税務上は「一時所得」として扱われることが一般的です。
一時所得の場合、受け取った配当金から50万円の特別控除額を差し引いた金額の2分の1が課税対象となります。
例えば、配当金が100万円の場合、以下のような計算になります。
課税対象=(100万円-50万円)×1/2=25万円
よって、25万円が課税所得として加算されます。ただし、保険の種類や契約内容によって税務処理が異なる場合があるため、具体的な税額については税理士や保険会社に確認しましょう。
保険金受け取りと同時
保険金受け取りと同時に配当金を受け取る場合、配当金は保険金と同様の税務処理が適用されます。
死亡保険金や満期保険金を一時金で支払った後は保険契約が消滅するため、配当金も保険金として扱われます。
具体的な課税方法は、契約者と受取人の関係によって以下のように決まります。
| 契約者と受取人の関係 | 保険金の内容 | 課税される税金の種類 |
|---|---|---|
| 契約者と受取人が同一 | 養老保険などの満期保険金 | 一時所得 |
| 契約者と受取人が相違する | 満期保険金や死亡保険金 | 贈与税 |
| 受取人が契約者の遺族 | 死亡保険金 | 相続税 |
なかでも、税負担が最も重くなるケースは贈与税で、配当金が加わることにより、税金の負担がさらに上がってしまう可能性があります。
税負担を軽減するためにも、満期保険金なら一時所得、死亡保険金なら相続税の対象となるように受取人を設定するのがおすすめです。
保険の種類によっても課税対象になる場合がある【参考】
保険の種類によっても課税対象になる場合があるので注意が必要です。
例えば解約返戻金が発生する生命保険商品の場合、解約によって一定額を超える利益を受け取ると一時所得の対象となり税金がかかります。
一時所得は、解約返戻金から支払った保険料の総額を差し引いた利益部分から50万円の特別控除を引いた金額が対象となります。
計算式は以下のとおりです。
一時所得=(解約返戻金-支払った保険料総額-50万)×1/2
また、近年では解約返戻金の設定が異なる以下2つのタイプの保険商品が増えてきています。
- 無解約返戻金型保険:解約返戻金がない
- 低解約返戻金型保険:通常よりも解約返戻金が少なく設定されている
解約返戻金がない、または利益が50万円未満なら税金はかかりませんが、将来の解約時の資金活用を考えている場合は、加入する保険商品の特徴をよく確認しておきましょう。
まとめ:5年ごと利差配当付き保険に関する相談はマネーキャリアへ
ここまで、5年ごと利差配当付き保険の仕組みやメリット・デメリット、課税の仕組みなどを紹介してきました。
5年ごと利差配当付き保険は保障と資産形成の両方を期待できる一方で、配当金の支払いは保証されていない点や6年目の契約応当日まで継続する必要がある点などデメリットもあります。
また、保険料が割高になる傾向や資産形成としてはリターンが小さいというデメリットもあるため、自分の加入目的にあった保険を選ぶことが重要になります。
「保険の選び方が分からない」「少額でもいいから保障を受けつつもリターンが欲しい」という方はぜひマネーキャリアの無料相談窓口にご相談ください!
保険・資産形成の専門家(FP)が数十社の中から保険商品を比較し、あなたに合った保険を提案いたします!また、その前段階としてあなたの家計状況や加入目的などを元にした利差配当付保険の適性度についても解説するのでぜひご相談ください!
オンラインで手軽に相談できるので気になる方は下のリンクからお問い合わせください。