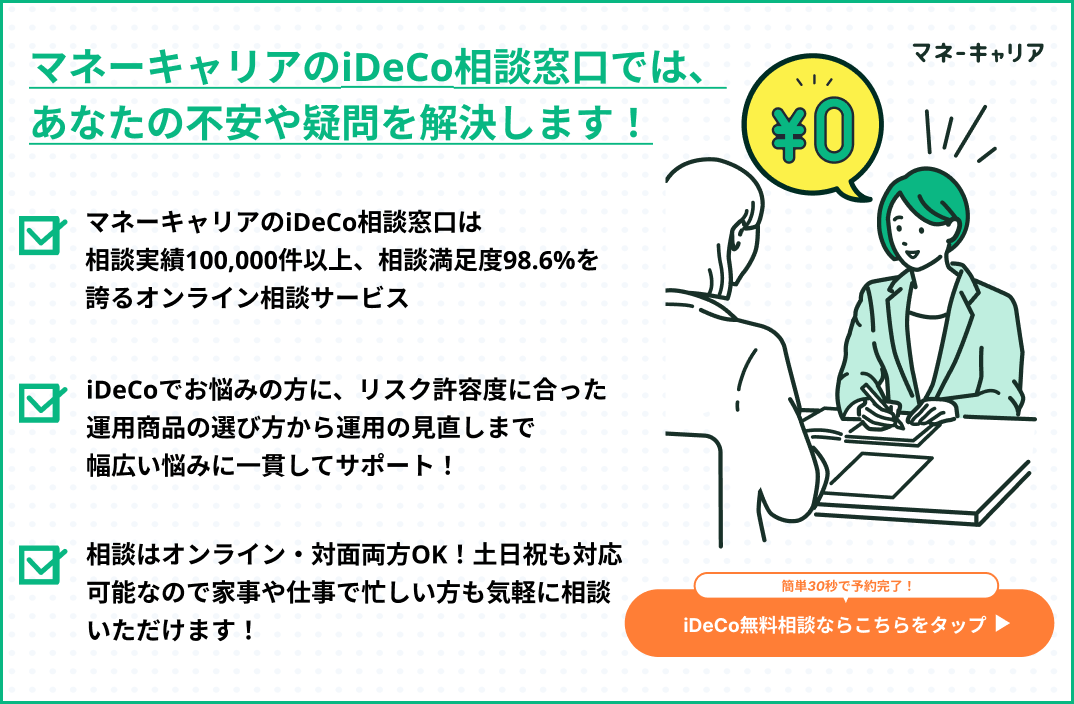この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。メディア実績:<テレビ出演>テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ!」
>> 谷川 昌平の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- iDeCoが50歳からでも無意味ではない!大丈夫と言われる理由とは?
- 加入年齢が65歳未満までに伸びたから
- 所得税と住民税が軽減されるから
- 元本確保型商品も選べてリスクを抑えられるから
- iDeCoは50歳からでも大丈夫!迷ったら無料FP相談を活用しよう
- 50歳からiDeCoを始める際の注意点3つ
- 加入期間が短いと受取年齢が61歳以降になる
- 受け取り時に税金がかかる場合がある
- ふるさと納税の上限額が下がる場合がある
- あなたにぴったりの方法は?FPと一緒に最適なiDeCoの運用法を見つけよう
- 50歳からのiDeCoについてよくある質問
- 50歳から始めるなら、iDeCoと新NISAのどっちを優先すべき?
- iDeCoの手数料はどのくらいかかりますか?
- もし運用中に自分が死亡したら、iDeCoの資産はどうなりますか?
- 【まとめ】iDeCoは50歳からでも十分効果あり!ライフプランと併せて判断を
iDeCoが50歳からでも無意味ではない!大丈夫と言われる理由とは?

「iDeCoは若いうちから始めないと意味がない」と思っていませんか?確かに、長期運用による複利効果は魅力ですが、50歳からでもiDeCoを始めるメリットはしっかり存在します。
むしろ、老後資金の準備を本格的に考えるこの年代だからこそ、iDeCoの恩恵を効率よく受けられる可能性もあるのです。
ここでは、50歳からでもiDeCoが「無意味ではない」と言われる理由を、以下の2つの視点から解説します。
- 加入年齢が65歳未満までに伸びたから
- 所得税と住民税が軽減されるから
- 元本確保型商品も選べてリスクを抑えられるから
制度の変更や税制優遇を正しく理解すれば、50代からのiDeCo加入でも十分に効果的な資産形成が可能です。
加入年齢が65歳未満までに伸びたから
所得税と住民税が軽減されるから
元本確保型商品も選べてリスクを抑えられるから
iDeCoは50歳からでも大丈夫!迷ったら無料FP相談を活用しよう


50歳からiDeCoを始める際の注意点3つ

50歳からでもiDeCoを始めるメリットは多くありますが、始める前に知っておきたい注意点も存在します。特に、加入期間が短くなることで発生する制限や、他の制度との関係による影響には注意が必要です。
制度の仕組みを正しく理解しておくことで、思わぬ落とし穴を避け、より効果的に活用することができます。
ここからは、50歳からiDeCoを始める際に押さえておきたい注意点を、以下の3つの観点から解説します。
- 加入期間が短いと受取年齢が61歳以降になる
- 受け取り時に税金がかかる場合がある
- ふるさと納税の上限額が下がる場合がある
これらのポイントを理解しておくことで、50代からのiDeCo活用をより安心・確実なものにすることができます。
加入期間が短いと受取年齢が61歳以降になる
iDeCoでは、60歳になったらすぐに受け取れるわけではありません。原則として、「通算加入者等期間(iDeCoや企業型DCなどの加入年数)」が10年以上必要で、これを満たさない場合は受取開始年齢が遅れます。
例えば、50歳からiDeCoを始めて10年加入すれば60歳で受け取れますが、55歳から始めた場合、通算加入期間が5年となるため、受取開始は65歳になります。
以下の表を参考に、加入年齢に応じた受取可能年齢を確認し、ライフプランと就労予定をふまえたうえで、無理のない計画を立てましょう。
| iDeCoの加入開始年齢 | 通算加入者等期間 | 受取可能年齢 |
|---|---|---|
| 50歳 | 10年以上 | 60歳から |
| 52歳 | 8年以上10年未満 | 61歳から |
| 54歳 | 6年以上8年未満 | 62歳から |
| 56歳 | 4年以上6年未満 | 63歳から |
| 58歳 | 2年以上4年未満 | 64歳から |
| 59歳 | 1ヶ月以上2年未満 | 65歳から |
※通算加入期間が1ヶ月未満の場合、受け取りはできません。
受け取り時に税金がかかる場合がある
ふるさと納税の上限額が下がる場合がある
あなたにぴったりの方法は?FPと一緒に最適なiDeCoの運用法を見つけよう

50歳からのiDeCoについてよくある質問

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、50歳からでも加入できる制度として注目されていますが、「本当に始めて大丈夫?」「他の制度とどう使い分けるべき?」など、疑問や不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
ここでは、50代からiDeCoを検討する方が特に気になりやすいポイントについて、よくある質問形式でわかりやすく解説します。
- 50歳から始めるなら、iDeCoと新NISAのどっちを優先すべき?
- iDeCoの手数料はどのくらいかかりますか?
- もし運用中に自分が死亡したら、iDeCoの資産はどうなりますか?
制度の仕組みや活用方法を正しく理解することで、50代からでも安心して資産形成を始めることができます。
50歳から始めるなら、iDeCoと新NISAのどっちを優先すべき?
iDeCoの手数料はどのくらいかかりますか?
iDeCoには、制度の利用にあたってさまざまな手数料が発生します。主な費用としては、口座開設時の初期手数料、毎月かかる運用管理手数料、受取時の給付手数料などがあります。
これに加えて、選んだ商品によっては信託報酬(運用管理費用)がかかるため、金融機関や商品を選ぶ際にはコスト面もよく確認することが大切です。以下は、一般的な手数料の目安です。
| 手数料の種類 | 金額の目安(税込) | 説明 |
|---|---|---|
| 加入時手数料 | 2,829円(初回のみ) | 国民年金基金連合会に支払う初期費用 |
| 口座管理手数料 | 月額171円〜(年間2,052円〜) | 運営管理機関や信託銀行に支払う基本費用 |
| 給付時の手数料 | 440円/1回 | 受け取りのたびにかかる手数料 |
| 信託報酬(商品ごと) | 年0.1〜1.0%程度 | 投資信託などの運用商品の管理費用 |
※運営管理機関によって手数料は異なるため、比較検討が重要です。
もし運用中に自分が死亡したら、iDeCoの資産はどうなりますか?
【まとめ】iDeCoは50歳からでも十分効果あり!ライフプランと併せて判断を