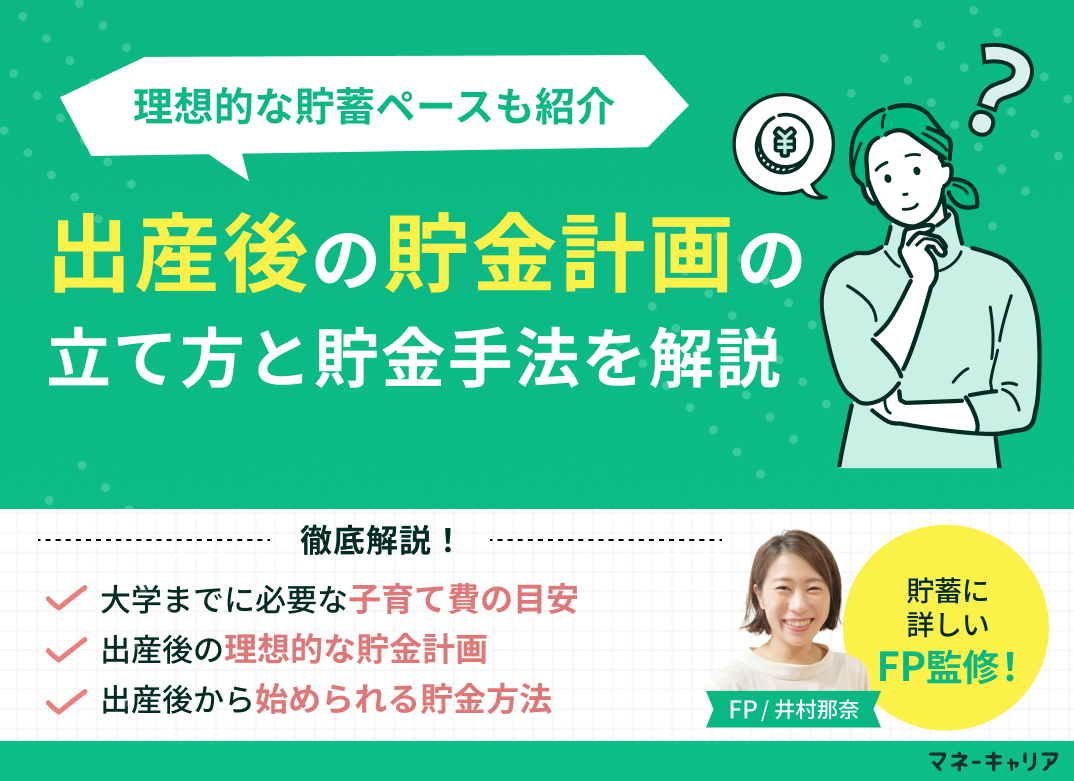
内容をまとめると
- 出産後の貯金計画においては、教育費や養育費など将来の支出を見据えと、家計の不安を減らすことができます。
- 積立定期預金や学資保険などの手段を比較し、自分に合った貯金方法を選ぶことが大切です。
- 必要な子育て費の目安や支出タイミングを把握しておくことで、無理のない範囲で長期的な資金計画が立てやすくなります。
- 家計の整理や将来設計に不安がある方は、相談実績10万件超・満足度98.6%超のマネーキャリアで、専門家(FP)から無料アドバイスを受けることをおすすめします。

この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。メディア実績:<テレビ出演>テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ!」
>> 谷川 昌平の詳細な経歴を見る
この記事の目次
大学までに必要な子育て費の目安
大学までに必要な子育て費の目安を、2つの視点から解説します。
紹介する費用は以下のとおりです。
- 教育費は1人あたり814万円〜
- 養育費は1人あたり1,169万円〜
教育費とは、授業料や入学金・教材費など、学校にかかるお金のことです。
対して養育費は、食費・衣類費・医療費・お小遣いなど、学校以外の日常生活にかかるお金を指します。
合計すると、1人あたり2,000万円以上かかるかかるケースもあります。
費用の全体像を早めに把握しておくことで、将来の支出に備えた貯金のペースや方法も見通しやすくなるので、ぜひ参考にしてください。
教育費は1人あたり814万円〜
教育費は1人あたり814万円〜と把握しておくことで、大学までに必要な貯金額や積立ペースを逆算しやすくなります。
進学先によって必要な金額が大きく異なるため、将来の支出に備えて、早めに貯金計画を立てやすくなるからです。
文部科学省の調査をもとにすると、すべて公立に進学した場合は約814万円、すべて私立なら約2,362万円が必要です。
以下の表は、幼稚園から大学までにかかる主な教育費の目安です。
| 公立 | 私立 | |
|---|---|---|
| 幼稚園(3年間)(※1) | 約56万円 | 約104万円 |
| 小学校(6年間)(※1) | 約202万円 | 約1,097万円 |
| 中学校(3年間)(※1) | 約163万円 | 468万円 |
| 高校(3年間)(※1) | 約179万円 | 309万円 |
| 大学(4年間)(※2) | 約214万円 (国公立) |
約384万円 |
| 総額 | 約814万円 | 約2,362万円 |
※1参照:令和5年度子供の学習費調査|文部科学省
※2参照:国公私立大学の授業料等の推移|文部科学省
なお、大学費用は授業料のみを記載していますが、実際は入学金・教材費・施設費なども必要になります。
特に大学進学時は支出が集中しやすいため、子どもが小さいうちから無理のない範囲で備えておくと安心です。
養育費は1人あたり1,169万円〜
養育費は1人あたり1,169万円〜と把握しておくことで、日々の家計や将来の出費を見通しやすくなります。
養育費とは、食費・衣類費・医療費・生活用品・お小遣いなど、学校外の生活にかかるお金を指します。
以下は、教育段階ごとの年間養育費と在籍年数から算出した目安額で、合計すると1,169万円になります。
| 教育段階 | 年間費用 | 在籍年数 | 計 |
|---|---|---|---|
| 幼稚園 | 約55万円(※1) | 3年 | 55万円 × 3 = 165万円 |
| 小学校 | 約57万円(※1) | 6年 | 57万円 × 6 = 342万円 |
| 中学校 | 約65万円(※1) | 3年 | 65万円 × 3 = 195万円 |
| 高校 | 約65万円(※1) | 3年 | 65万円 × 3 = 195万円 |
| 大学 | 約68万円(※2) | 4年 | 68万円 × 4 = 272万円 |
| 総額 | - | - | 約1,169万円 |
※1引用:平成21年度インターネットによる子育て費用に関する調査|内閣府
養育費は、学費のように一度に大きな支出が発生するわけではないため、日常の家計からまかなう家庭も多いでしょう。
とはいえ、食費や衣類費・お小遣いなどは年齢とともに増えやすいため、少しずつでも積み立てておくと、将来的な負担をやわらげることができます。
なお、高校のデータは中学校の数値を参考にしていますが、実際はやや高くなる傾向があると考えられます。
出産後の理想的な貯金計画
出産後の理想的な貯金ペースは、子どもの年齢に応じて変化します。
以下は、将来の“教育費”に備えて、今からどのくらい貯めていけばいいかを考えるための目安です。
| 年齢 | 毎月の目安金額 |
|---|---|
| 0~6歳まで | 毎月3~5万円 |
| 7~15歳まで | 毎月2~3万円 |
| 16~18歳まで | 毎月2~3万円 |
0〜6歳までは、比較的お金がかかりにくい"貯め時"といえ、この時期にまとまった金額を積み立てておけると、あとがぐっとラクになります。
上表のペースで貯金を続けていけば、高校卒業時点までに最大で852万円が貯まる見込みです。
この金額は、大学入学時に必要となる教育費を上回るケースもありますが、高校在学中にも塾代・受験費用・教材費などがかかるため、多めに備えておくと安心です。
無理のない範囲で積み立てておくことで、進路の選択肢を広げたり、将来の不安をやわらげたりしやすくなります。
なお、ここで紹介しているのは“教育費”に備えるための貯金計画であり、食費や生活用品などの“養育費”は、日々の家計のなかでまかなうご家庭が多いのが実情です。
出産後の貯金方法
出産後におすすめの具体的な貯金方法を、4つ解説します。
紹介する方法は以下のとおりです。
- 積立定期預金
- 学資保険
- 個人向け国債
- 投資信託
それぞれの仕組みやメリットを知ることで、収入やライフスタイルに合った方法を選びやすくなるので、ぜひ参考にしてください。
積立定期預金
学資保険
個人向け国債
投資信託
出産後の貯金計画で悩んだら専門家(FP)に無料相談がおすすめ
出産後の貯金計画に関するよくある質問
出産後の貯金計画に関するよくある質問を、3つ解説します。
紹介する質問は以下のとおりです。
- 教育費をどうしても準備できなかった場合はどうしたらいいですか?
- 出産前の貯金額の目安はいくらですか?
- 出産前に貯金がない場合はどうすればいいですか?
よくある不安や疑問にあらかじめ目を向けておくことで、貯金計画の全体像がつかみやすくなるので、ぜひ参考にしてください。
教育費をどうしても準備できなかった場合はどうしたらいいですか?
出産前の貯金額の目安はいくらですか?
出産前には最低50万円、できれば100万円ほど準備しておくと安心です。
50万円の内訳には、例えば妊婦健診費用や入院時の自己負担、おむつやミルク代(3ヵ月分)、生活費1ヵ月分などが含まれます。
一方、100万円を用意できば、帝王切開や合併症などで医療費が増えた場合や、産後ケアサービスの利用にも対応しやすくなります。
こうした追加支出も想定しておくことで、産前産後の金銭的不安を減らすことができます。
ただし、必要な金額は家庭の状況や出産スタイルによって異なります。
自分たちのライフプランに合わせた備えを検討しましょう。
出産前に貯金がない場合はどうすればいいですか?
出産費用の準備が難しい場合は、公的制度や一時的な資金調達の選択肢を早めに検討することが大切です。
例えば、自治体によっては"出産育児一時金の貸付制度"を設けており、出産前に申請しておくことで、分娩費用の一部を前もって受け取れるケースがあります。
また、医療機関によってはクレジットカード払いに対応していることもあるため、現金が手元にないときの支払い手段として利用できる可能性もあります。
制度の内容や支払い方法について事前に確認・相談しておくことで、無理のない形で出産に備えることができます。
出産後の貯金計画は早めに立てて将来の安心を手に入れよう【まとめ】
出産後の貯金計画は、できるだけ早めに立てておくことで、将来への不安を減らして安心して子育てに向き合うことができます。
具体的には、大学までにかかる教育費・養育費の目安を把握したうえで、積立定期預金・学資保険などを活用し、自分に合ったムリのない貯金スタイルを見つけることが大切です。
とはいえ、一人で必要な金額を試算し、最適な貯金方法を選ぶのは簡単ではありません。
出産後の家計管理に不安を感じている方や、どの方法で貯金を進めるべきか迷っている方は、専門家(FP)への相談をおすすめします。





























