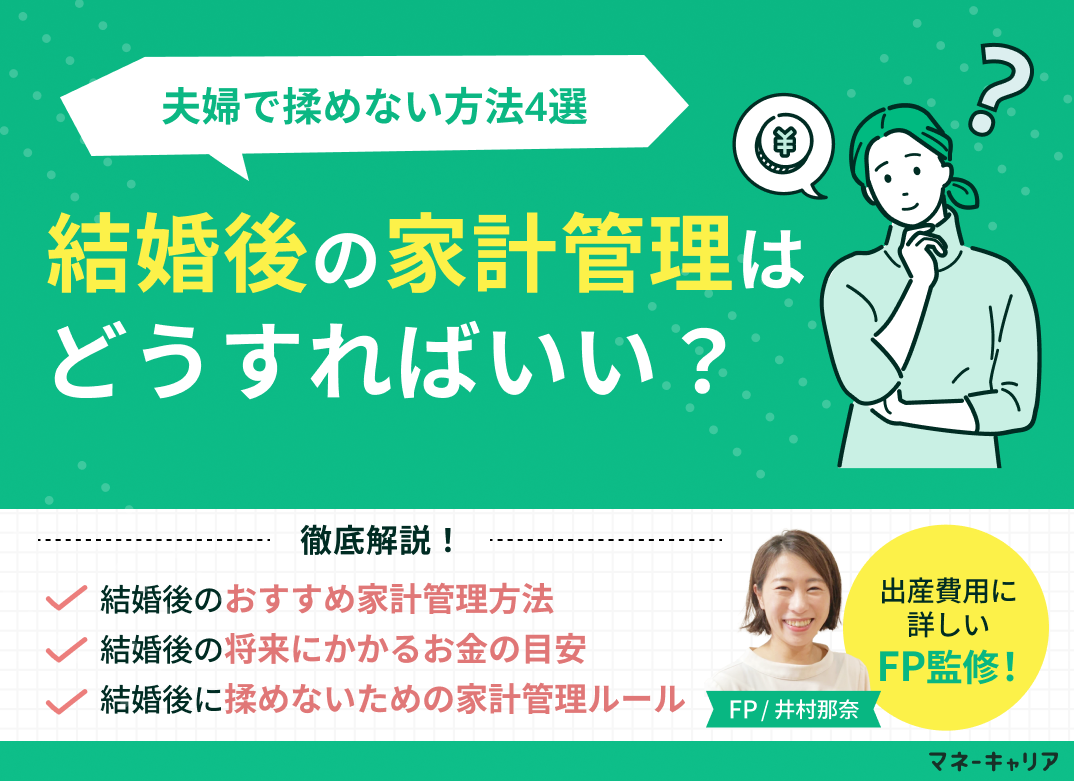
・「お金のことで喧嘩しない夫婦関係を築きたい」
内容をまとめると
- 結婚後の家計管理には「共有口座制」や「別財布制」など複数の方法がある
- 子育てや住宅・老後の費用も見据えて貯蓄計画を立てることが大切
- 夫婦で揉めないためには、お金の価値観を共有しルールを明確にすることが必要
- マネーキャリアでは、夫婦に合った家計管理や将来に備える貯蓄プランを提案してもらえる

この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。メディア実績:<テレビ出演>テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ!」
>> 谷川 昌平の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- 結婚後の家計管理はどうする?おすすめの方法4選
- 財布をひとつにまとめる「共有口座制」
- 項目別に支払いを分担する「分担制」
- 生活費だけ共有する「ハイブリッド制」
- 完全に1人が家計管理を担う「お小遣い管理制」
- 結婚後はいくら貯めるべき?将来かかるお金の目安
- 子育てにかかるお金
- マイホーム購入・住宅ローン
- 老後に備えるべき生活費
- 夫婦喧嘩を防ぐ!家計管理で揉めない3つのルール
- 最初にお金の価値観をすり合わせよう
- 大きな支出は必ず事前相談するルールを決める
- 定期的に「家計ミーティング」をする
- 結婚後の家計管理に関するよくある質問
- 家計簿はつけるべき?
- 収入差がある場合はどう考える?
- 家計管理について話し合うタイミングはいつがいい?
- 結婚後の家計管理でお悩みならお金のプロ「マネーキャリア」に相談
結婚後の家計管理はどうする?おすすめの方法4選
結婚後の家計管理はどうするのがよいか、多くの夫婦が最初にぶつかる悩みです。
価値観や収入の違いがあるからこそ、どのスタイルが合うかを知っておきましょう。
また、どの方法にもメリット・デメリットがあり、夫婦間の性格やライフスタイルによって向き不向きも分かれます。
以下では、代表的な家計管理法を4つご紹介します。
- 財布をひとつにまとめる「共有口座制」
- お互いが自由に管理する「別財布制」
- 固定費などを役割分担する「分担制」
- 一部のみを共有する「ハイブリッド制」
- 片方が家計を一任する「お小遣い管理制」
それぞれの仕組みや特徴を理解しながら、自分たちに合う方法を見つけていきましょう。
財布をひとつにまとめる「共有口座制」
財布をまとめて管理する「共有口座制」は、もっともオーソドックスな家計管理方法です。
共通の口座を作り、生活費を入金することで、支出の全体像がわかりやすくなります。
夫婦それぞれが収入の一定割合を口座に入れ、家賃や食費・水道光熱費などをすべてそこから支払うイメージです。
項目別に支払いを分担する「分担制」
分担制は、生活費の項目ごとに支払いを分け合う家計管理スタイルです。
「家賃は夫、食費は妻」といった具合に役割を固定することで、責任の所在が明確になります。
この方法は、支出のバランスを話し合って決めれば公平感を保ちやすいという利点がありるでしょう。
生活費だけ共有する「ハイブリッド制」
「ハイブリッド制」は、共有と別管理のいいとこ取りをした家計の分け方です。
たとえば、家賃・水道光熱費・食費だけは共通口座から出し、それ以外の趣味や個人費は別管理にするという方法です。
共同生活に必要な費用をしっかり管理しつつ、それぞれの自由も確保できます。
完全に1人が家計管理を担う「お小遣い管理制」
「お小遣い管理制」は、どちらか一方が家計全体を管理し、もう一方にお小遣いを渡すスタイルです。
この方法は、管理する側が支出をコントロールしやすく、貯金や資産形成が進みやすい傾向があります。
夫が全収入を妻に預け、毎月5万円を自由に使えるお金として受け取るといった運用が一般的です。
結婚後はいくら貯めるべき?将来かかるお金の目安
結婚後はいくら貯めるべきかは、将来的なライフイベントを見据える必要があります。
そこで、将来のライフイベントを整理してみましょう。
- 子育てにかかるお金
- マイホーム購入・住宅ローン
- 老後に備えるべき生活費
これらの支出を前提に貯蓄目標を設定すれば、自信を持って将来に備えられます。
子育てにかかるお金
子育てには膨大な費用がかかるため、早めの準備が不可欠です。
文部科学省などの調査によると、子ども1人あたりにかかる教育費は約1,000万〜2,000万円にもなります。
たとえば、すべて公立で育てた場合は約1,000万円ですが、私立を選ぶと一気に2倍近く跳ね上がります。
マイホーム購入・住宅ローン
マイホームを購入する際には、頭金や諸費用だけで数百万円の出費が発生します。
また、その後も20〜35年は毎月住宅ローン返済をし続けなければなりません。
たとえば3,000万円の物件を35年ローンで組んだ場合、毎月の返済額は約8万円〜10万円かかります。
老後に備えるべき生活費
老後の生活を安定させるには、現役時代からの備えが重要です。
平均寿命が延びるなか、「老後資金2,000万円問題」は決して他人事ではありません。
たとえば、年金以外に月5万円の不足がある場合、30年で1,800万円が必要になります。
夫婦喧嘩を防ぐ!家計管理で揉めない3つのルール
家計の管理をめぐる夫婦喧嘩は、早い段階で防ぐことが可能です。
ここでは、揉めずに済む家計管理のための3つのルールを紹介します。
- お金に対する価値観のすり合わせを行う
- 大きな支出は必ず事前に相談する
- 定期的に「家計ミーティング」を実施する
それぞれを丁寧に実践することで、結婚後の家計管理がスムーズになり、夫婦の信頼関係も深まります。
最初にお金の価値観をすり合わせよう
夫婦間で家計管理をうまく進めるには、最初にお金の価値観を共有することが不可欠です。
なぜなら、育った環境や経験によって、支出や貯金に対する考え方が大きく異なるからです。
たとえば、妻は「車は現金で買うべき」と考える一方で、夫は「ローンは当たり前」と思っているケースもあります。
大きな支出は必ず事前相談するルールを決める
大きな買い物をするときには、事前に相談するルールを決めておくと安心です。
突然の出費が家計に与えるインパクトが大きく、報告していないと後から揉める原因になりやすいでしょう。
たとえば、「3万円以上の買い物は必ず相談する」といった具体的な金額ラインを設定しておくと、トラブル防止に役立ちます。
定期的に「家計ミーティング」をする
「家計ミーティング」を定期的に行うことで、お互いの不満や改善点を早期に共有できます。
月1回でも5分でもよいので、家計の状況を一緒に確認する場を作ることが大切です。
「今月は食費が高かった」「旅行費が予算オーバーだった」など、振り返りを通じて改善案が見えてきます。
結婚後の家計管理に関するよくある質問
結婚後の家計管理に関する悩みは、どの夫婦にも共通しています。
ここでは、多くのカップルが悩む3つのポイントを取り上げて解説します。
- 家計簿をつけるべき?
- 収入に差がある場合はどう考える?
- 家計管理の話し合いうタイミングはいつがいい?
これらの疑問を解消することで、結婚後の家計管理に対するヒントが得られるでしょう。
家計簿はつけるべき?
家計管理を明確にするためには、家計簿をつけることが非常に有効です。
理由は、収支の流れを「見える化」することで、無駄な支出や改善点がはっきりとわかるからです。
毎月なんとなくお金が減っている…と感じていた場合でも、家計簿をつけると「外食費が多い」「サブスクが多い」など具体的な原因に気づけます。
収入差がある場合はどう考える?
収入に差がある場合は、「割合で分担する」考え方を取り入れるのがおすすめです。
なぜなら、金額で均等に分けると、収入が少ない側の負担感が大きくなり、不公平感が生まれやすくなるからです。
家計管理について話し合うタイミングはいつがいい?
家計管理の話し合いは、結婚前〜結婚直後の早い段階で行うのが理想です。
共通のルールを先に決めておけば、生活が始まってからのトラブルを防ぎやすくなるでしょう。
具体的には、新居に引っ越す前や、共通口座を作るタイミングで話し合うのがおすすめです。
結婚後の家計管理でお悩みならお金のプロ「マネーキャリア」に相談
結婚後の家計管理について、主な方法4つとそれぞれのメリット・注意点を紹介しました。
これから家計をどう管理するか悩んでいる方は、まずは夫婦でお金の価値観を共有し、どの管理方法が合っているかを話し合うところから始めてみてください。
とはいえ、「夫婦で収入差がある」「貯金が思うようにできない」「何から手をつけていいかわからない」と感じる方も少なくありません。
そんなときは、お金のプロに頼るのが家計管理成功の近道です。
「マネーキャリア」では、結婚後の家計管理・貯蓄の目標設定・将来の支出に向けた準備方法などについて、何度でも無料で相談できます。
女性FPが多数在籍しており、スマホから簡単に申し込みが可能なので、夫婦で気軽に利用しやすいのもポイントです。
家計管理に少しでも不安がある方は、一度「マネーキャリア」に相談してみてはいかがでしょうか。
あなたの家庭にぴったりの管理方法がきっと見つかります。





























